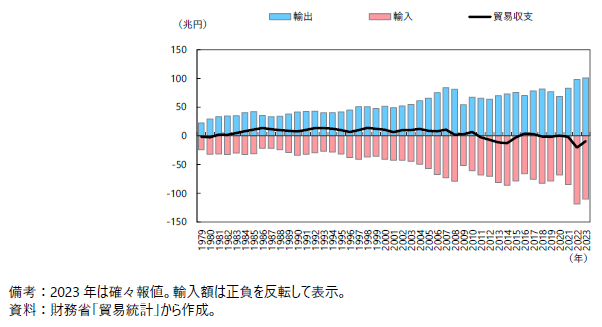空気感からの自由
言論の自由が危機に瀕しています。と言っても、検閲や法的規制など、政府からの自由ではなくて、巷の空気感からの自由です。SNS等の言論空間のなかで、先鋭化したコンテンツを発信する発信強者がほぼ無制限の自由を謳歌し、いじめの構造にも似た独特の空気感によって、その他の者の発信の自由が委縮し、穏健で成熟した議論の積み上げがなくなり、発信強者が世論を形成し、健全な言論空間どころか健全な民主主義にまで影響を与えうるようになっているのではないか。選挙に対して海外から組織的な影響力工作がなされる可能性すらあるのではないか。そうした現状を前に、様々な方面から懸念が表明されています。
先鋭化するSNSの脅威
極端な意見がバズり拡散される傾向にありますが、そうしたコンテンツは強い発信動機のある先鋭的な層から発信されます。一方で穏健で思慮深い層はそもそも敢えて情報発信をする動機に乏しく、先鋭層に対して敢えて戦いを挑もうとするはずはなく、結果的に先鋭な意見が穏健な意見を押しつぶす傾向になります。その結果、極端な意見がSNSを埋め尽くし、健全な意見集約にはならず、全体が先鋭化します。かつて英元首相ボリス・ジョンソンが退任するとき「我々は国民の代表だ。ツイッターの代表ではない。」という演説をしていたのが印象的でした。
政治家も回転すしの醤油瓶
先鋭的な意見であっても、健全な動機で発信している人ももちろんいますし、自らの意見に反対する意見に、全ての人が攻撃を仕掛けるわけでもありません。ただ、問題とされるべきは、コンテンツとは関係なくインプレッション獲得による収益最大化を狙っている者です。いわゆるアテンション・エコノミーです。大規模災害のときに収益目的で扇動的な偽情報を拡散する輩がいることは皆様もご存じだと思います。人の不幸をカネにするとは非道だと私は思います。
政治がそうした収益目的のインフルエンサーと合体すると、偽情報が拡散しやすい。政治に無関心でも政治家をネタに収益化できるからです。ほぼ何も考えずに面白おかしく収益化できるからです。政治家の発信を多少細工して先鋭化させれば収益化できてしまいます。切り抜き動画などを作成している間に偽情報になっていくというものです。これは昔、回転すしの醤油瓶を舐め回すコンテンツでインプレッションを獲得し収益最大化を狙った者と同じ動機です。舐め回された政治家はたまったものではなく、普段から舐めまわされないようにおとなしくしている他ありません。ある種、政治家が消費されている状態です。
テレビをしのぐSNS等の広告収入
テレビ等の放送業界は基本的には広告収入が収益の中心になります(もちろんそうではない放送会社もありますが)。従って、広告主に極端に有利な番組内容にならないようにガバナンス体制を整えています。ただ報道の自由は大切なので、政府は当然ながら厳しい個別規制ではなく、合理的な範囲のルールということになります。その意味で、放送業界は無制限の自由を獲得しているわけではなく、健全な報道の自由や言論の自由を担保するために、放送法という業法の下で、自主的な取り組みをしてきた業界です。
一方でSNS等は業法規制対象では当然なく、唯一、情報流通プラットフォーム対処法が整備されているだけで、基本的には事業者の自主努力に大きく委ねられています。もちろん自主的だからダメということではなく、事業者自身も相当の労力を費やしていることは承知をしていますが、こうした自主努力は世論に弱い。従って、放送法に類する何らかの法的基盤が私は必要だと思っています。
情報を多くの人に伝える手段という意味では、もはやSNSは放送事業者と変わりません。SNSの空気感による言論危機も、戦前の反戦国賊の空気感と同じで、基本的には国民リテラシーの問題ではあるのですが、だからと言って先鋭化し始めた社会のなかで、何もしないわけにはいかないと思っています。
SNSの健全な発展のために何をするか
ポイントは、SNSにあふれる不適切な情報、嘘の情報とをどのように扱うのかです。何が嘘で何が不適切かを行政が判断するという方向には絶対にならないので、ビジネス全体の健全化のための取り組みが求められます。
既存ビジネスモデル
SNSは1人で気軽に無料で世界中に情報を発信できますが、インプレッション(閲覧数)やエンゲージメント(反応)に応じて収益化できるため、刺激的な情報や正確ではない情報でも、バズれば得だ、と考えるようになります。「テレビは絶対報じない○○」とか「削除覚悟の暴露」とかのタイトルをご覧になったかたもいると思います。いわゆる炎上商法もあるでしょう。
プラットフォーム事業者(PF事業者)の収益は主に広告主です。PF事業者からみると、無料でアカウントを提供している一般ユーザが、コンテンツ配信でインプレッションを稼いでくれて初めて、広告主から広告料を徴収できる。そういう意味ではユーザあってのPF事業者なのですが、広告主から見ると、問題のある不適切コンテンツばかり発信しているようなユーザのチャンネルで広告をだされると、評判が下がることになります。
方向性
既に党として提案している内容は報道にもある通りで、一部の収益停止とアカウント実名公表選択の義務化ですが、そもそもPF事業者の健全性を広告主が評価できる仕組みは検討の余地があると考えています。コーポレートガバナンスコードという考え方に近いのかもしれません。しっかりと検討し実装していきたいと思います。