
日本が世界の中で存在感を示せたのも、国際的にも経済的豊かさを享受できたのも、産業があっての話です。もちろん産業があるのは教育や研究開発力があるからですし、産業が安心して活動できる外交や安全保障や社会保障や減災防災の基盤があるからで、加えて言えば産業といっても最先端産業ではなくてもそれを支えるあらゆる産業があるからですが、今日はその産業全体の現状について触れたいと思います。
■経常収支が過去最高でも
まず共有したいのが昨年の国際収支において経常収支が過去最高を記録したということです。過去の活動のお陰です。すなわち日本が海外子会社から受け取る配当などが爆増したということで、29兆円(前年比+7兆円)にも上るということです。これはこれでとても良いことです。
問題は、これで日本人の懐が豊かになっているのかです。答えはNo。
理由は簡単で、(事柄を単純化すれば)海外子会社が収益を出しても海外に再投資されている額が多いからです。日本には戻ってきていない。
では経常収支全体の構造はというと、経常収支(+29兆円)=貿易収支(▲4兆円)+サービス収支(▲3兆円)+所得収支(40兆円)+政府資金移転(▲4兆円)です。
すなわち日本は国際収支の上では、かなり前から貿易やサービスでは飯を食っておらず、海外配当などで飯を食っている国になっているということです。
どうしてこうなってしまったのか。もう少し内情に触れたいと思います。
■貿易収支)輸出が減っているわけではない
ただ、日本製品が売れなくなっているわけではなく、堅調に増加しています。私が社会人になったころは50兆円くらいだったのが、今では100兆円を超えます。輸入も同様な傾向ですが、そのバランスが以前は10兆円黒字だったものが、今では4兆円の赤字ということです。
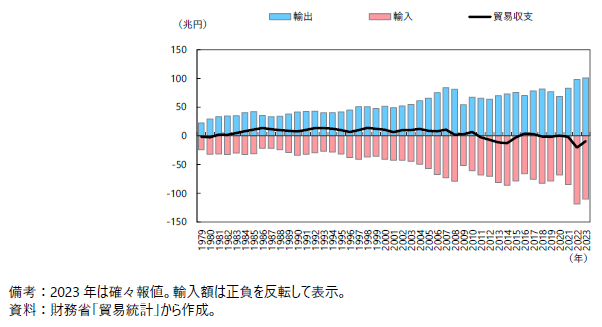
(経産省:貿易統計)
■サービス収支)要はデジタルサービス赤字
分かりやすく着目すべき項目をメインに単純化すると、デジタルサービス(※)の赤字7兆円や保険サービスの赤字2兆円を、知的財産黒字3兆円や外国人観光客黒字3兆円で埋めて、3兆円の赤字です。ただ、構造は単純ではありません。
(※)デジタルサービス)音楽や動画配信(著作権使用料)、クラウド(通信コンピュータ情報)、ネット広告(専門コンサル)など

(時事通信:デジタル関連収支(赤字額)の推移)
デジタルサービスについては、我々は恒常的にアマゾンやグーグルやユーチューブを使っていますが、国全体で言えば国民一人当たり7万円も海外にお支払いをしているということで、これが2030年には赤字10兆円になるといわれています。日本のデジタルサービスの供給力が決定的に弱く、改善すべき最大のポイントです。
再保険サービスについては、災害リスクに備えた損保会社の再保険市場の国際化進展が華々しく赤字が拡大の一途をたどっています。しかし保険会社が海外企業の買収によって所得収支の黒字化に貢献している部分もあり、リスクヘッジのためには不可欠なため、特に改善ということではなく動向を注視すべきです。
知的財産等使用料は黒字が拡大しています。海上貨物の赤字が拡大していることも併せれば、産業界が加工貿易から現地生産販売や海外拠点から第三国輸出に生産体制を変化させたことが主要因でしょう。
旅行収支は注目です。昨年は訪日外国人旅行者が47%割増えました。出国日本人も35%増えましたが収支は大きな黒字です。現在オーバーツーリズム対策が懸命に行われていますが喜ばしいことです。ただし、単純に中国に頼っていいのか、急な出国制限など経済的威圧のリスクがあるなかで、コントロールしなければなりません。
要はデジタルサービスの供給力を日本は持つべきで、赤字拡大に歯止めをかけないと、海外に国民一人当たり年間7万円も払うことを続けなければいけないわけで、今後ますます国益の海外流出は避けられない構造です。
■すなわち生産力・供給力の強化が急務
結局、リアルな産業では、人口減少で十分な将来展望が描けない日本市場よりも、海外市場を志向して生産体制を海外に移し、所得収支で黒字になっても再投資で金融収支を拡大しているので、日本には富が残らず、生産体制が海外に移ったので国内の中小企業含めたサプライチェーンに裨益することは少ない。また、デジタルサービスでもどんどん海外に支払っているという構図です。
こうした現状でただでさえ賃上げが進む大手企業に有利な所得控除拡大を行うのは、中小や低所得者に全く裨益しないどころか、格差が拡大することになるという構図であることを、どうか理解して頂きたいと切に思っています。むしろこれなら、定額減税であるべきです。サラリーマン減税の話をパートさんの就労調整の問題であるかのごとく103万円の壁とか言うから話が混乱しているとしか思えません。
しかしそれ以上に重要なポイントは、構造的に国益が流出しないような産業構造にすることであって、それは生産力・供給力を抜本的に強化することにほかなりません。
■なぜこうなってしまったのか
思えば初当選直後、日本の産業凋落を食い止めるため、国際競争力上不利にあった法人税実効税率を少なくとも諸外国並みに下げる運動に加担しました。実効税率が下がれば国内投資が活発になり、供給力低下に歯止めがかけられると踏みました。
しかし結局それから10年経過して見返すと、企業は投資を拡大してくれたはいいものの、海外投資を活発にする方向に向かった。思えば法人税実効税率の議論の直後に、人口減少や消滅可能性都市の話題が盛んになり、国内投資を阻んだのかもしれません。
今後のことで加えて言えば、トランプ2.0が始まりました。おそらく企業はこれまでにも増して、米国投資を考えるようになるはずです。
国内投資を拡大するために、政府が民間の代わりに投資することで官民の投資を誘発するという考え方、具体的には法人税実効税率見直しと官民国内投資拡大を主張する向きもあります。実際に現時点で着手することには反対ですが、国内投資目標を設定し、フォワードガイダンスで推進したうえで達成困難なら検討の可能性を示唆するくらいはしてもいいように思います。
また科学技術イノベーション政策の土台を築くことも重要です。来年から新たな基本計画が実行される予定で、現時点で策定に向けた議論が始まっています。
また投資に適した信頼されるマーケットを作るための努力も必要です。一見投資拡大には逆行するかに見えるかもしれませんが、確実に信頼を得られるラインは引いておくべきです。金融市場の整備に加え、投資審査や技術流出防止などに向けた努力も必要です。
いずれにせよ、政府が率先して生産力・供給力のための投資拡大を行わなければ、日本は何も残らない国、海外に行ける大企業だけが海外で稼いできて周辺産業には裨益しない国、すなわち典型的な格差社会の国に成り下がる可能性すらあります。
