梅雨が明け本格的な夏が当来いたしました。その夏本番、谷垣法務大臣と茂木経済産業大臣が、参議院候補者の三宅しんごさんの応援で、琴平・まんのう地区にお越しになります。お暑い中、またお忙しい中、恐縮ですが、お誘いあわせのうえ、ご来場賜りますよう、よろしくお願いします。
7月11日(木曜日)
18:30 琴平決起大会 上郷ふれあいセンター(谷垣大臣・茂木大臣)
19:00 まんのう決起大会 満濃農業改善センター(谷垣大臣)
梅雨が明け本格的な夏が当来いたしました。その夏本番、谷垣法務大臣と茂木経済産業大臣が、参議院候補者の三宅しんごさんの応援で、琴平・まんのう地区にお越しになります。お暑い中、またお忙しい中、恐縮ですが、お誘いあわせのうえ、ご来場賜りますよう、よろしくお願いします。
7月11日(木曜日)
18:30 琴平決起大会 上郷ふれあいセンター(谷垣大臣・茂木大臣)
19:00 まんのう決起大会 満濃農業改善センター(谷垣大臣)
七夕の7月7日を迎えました。織姫と彦星が年に1度だけ会える日だとされていますが、私自身は皆様に何度もお会いしたいと思いながら、参議院選挙の活動を続けています。始まって4日目になります。
非常に低調です。まず言えるのが関心の薄さ。だからこそ、もう一度、今回の参議院選挙の意味を考えてみたいと思いますし、それによって皆様に関心を持っていただきたいと思っています。
基本的に今回の選挙の争点は安倍内閣の評価以外にはありません。もちろん、財政や社会保障、国防や憲法など、喫緊の課題は山積しておりますが、選挙の争点にはなりにくい。であるならば、アベノミクスをやり続けさせていただけるかどうかしかないはずです。
政治は、何をやるか、という目的が重要ですが、リソースの少ない現状の日本では、何をどうやるか、という手段も重要です。アベノミクスの1〜2本目の矢がこれに相当します。ただ、危機の時には、何をどうやり続けるのか、という問題の方がはるかに重要なのです。
ただ、比較的うまくいった過去半年の経済政策。うまくいったから今後もやり続けさせてね、というのはオコガマシイというものです。だから、私は、一つのことをお約束して回っています。それは、驕らないで政策を断行するということの1点です。
生身の人間だろうが、ビジネスだろうが、政治だろうが、驕れるものは久しからずなのです。やらせてほしいと懇願する人が豹変し、許可を与えると驕り高ぶる様子を見れば、いくら結果を出していても続けさせるわけには行かないと考えるのが人間です。
私のキャッチコピーは「謙虚に真摯に大胆に」です。驕らず謙虚に、ただし謙虚はいいけど何もしなければ意味がないので、大胆にやるべきは大胆に行動する、そういう想いをこめて作ったコピーです。
三宅しんごさん。少し硬いイメージをもたれますが、中身のある人物です。何をどうやるか、という問題と、どうやり続けるか、という2つの根本課題に政治の最前線で取り組んでいただける方だと確信しています。
石破幹事長が再びお見えになります。来る10日、遊説しながら来県し、丸亀の県立競技場にて街頭演説を三宅しんご候補とともに行い、再度遊説しながら移動。夕刻から下記の予定で政見を賜ります。お忙しいとは存じますが、お誘いあわせのうえご来場賜りたくご案内申し上げます。
■7月10日(水曜日)
石破幹事長、来県! ~観音寺・大野原・豊浜
17:40 県立丸亀陸上競技場
18:30 観音寺決起大会 JA観音寺
19:00 大野原決起大会 大野原中央公民館
19:30 豊浜決起大会 豊浜公会堂
来る7月5日、安倍総理が来県、街頭にてお訴えをさせていただきます!
13:00- 高松 コトデン瓦町駅前
14:00- 坂出駅前
坂出には、私も参ります!
是非、お誘い合わせの上、多数のご来場をお待ちしております!

ダボス会議で名を知られる世界経済フォーラムの東京ミーティングに参加してまいりました。世界の皆様は完全にAbenomicsの勉強モード。最近、外的要因も相俟って株式市場も乱高下をしていますが、依然感心の最も高い問題です。
一方で、二番目に多い関心事は、少子高齢化にどのように対応するつもりなのかという問題。確かに労働人口が減って消費人口も減ったら経済は衰退する方向に向います。だから、移民政策を見直すか、高齢者や女性労働力を当面は積極的に活用するか。労働意識を改善することも一つの方向だと思います。
もちろん少子化に正面から取り組む必要があると思いますが、雇用労働政策や中小企業政策が成長戦略の中で最も重要な課題の一つだと思っています。
最近デモが激化していることで有名になっているトルコに強い関心を持っています。より正確には、シリアなどの中東情勢やそのアメリカの関与と、エネルギー政策です。数日前にもアラブの春と中東アフリカ政策と日本の関係を書かせていただきましたが、トルコは親アメリカ政策を歴史上採り続けており、アメリカもトルコを砦と思っている節があります。
今日、改めて自民党本部でトルコ内政に関する勉強会があり、中東の複雑さを再認識しました。紀元前後から言えば、トルコはローマ帝国の一部であり、5世紀の西ローマ帝国崩壊以降は東ローマ帝国の首都、コンスタンティノポリス(イスタンブール)として栄えた地域です。そして、15世紀の東ローマ帝国崩壊から、イスラムの支配が及び、オスマン帝国として繁栄を続け、ハドリアヌス時代のローマ帝国を彷彿とさせる広大な地域を統治するほどになった。そして、近代に入って第一次大戦前後になると、ナショナリズムの勃興によって完全に崩壊。その後、独立運動の英雄、アタチュルクが立ち上がり、現在のトルコの領土を勝ち取り、オスマン家を追放して、世俗主義の近代西洋風イスラム国家を作りました。
爾来、基本的にはトルコは親欧米国家でありつづけましたが、一方で今世紀に入って政治腐敗が横行し、それが嫌悪され、イスラム教保守主義が台頭し、現在のエルドアン首相率いる与党公正発展党がトルコ周辺地域に住む保守層から高い支持を得て安定した政権与党となっています。ただ、旧来の非宗教的な世俗主義が衰退したわけではなく、相変わらずこの世俗主義と保守主義の対立は、根深いものとなっているのが問題の一つです。
もう一つの問題がクルド人問題です。クルド人はアラブ人やトルコ人、ペルシャ人に次いで世界最大の国家を持たない民族集団ですが、トルコでは、政権から迫害されており、1980年代から常に国家にとっての悩みの種で、幾多のテロを経験しています。トルコの今回の暴動は、クルド人問題や前述の宗教感が直接のきっかけに繋がった節はなさそうで、どちらかと言えば強すぎて傲慢になりすぎた与党に嫌気をさした住民による単純な謀反がきっかけになっています。しかし、徐々にクルド人問題など、人種間対立につながりつつあるところが問題を複雑化しています。
傲慢になるとかくも弱体化するのかという典型で、あらためて謙虚さや真摯さを大切にしなければと思いますが、そうした2つの複雑な対立軸のなかで、混乱を放置しておくことは国際社会の利益に全く反します。なぜならば、トルコは中東の複雑な関係の最後の砦となっているからで、トルコの混乱は、中東全体に影響し、ひいてはアフリカまで影響を及ぼす可能性すら秘めています。
もちろん、イスラエルとならんでアメリカが信頼する中東国のトルコを、アメリカが放って置くはずはありません。事実、関係が悪くなっているイスラエルとトルコの間をとる作業をアメリカは行っています。しかし、内向き化が進むアメリカに中東関与を続ける体力があるのか、そして、先のブログでも触れましたが、アジアシフトを鮮明に打ち出しているアメリカですから、中東関与のインセンティブをアメリカは持ち続けることができるのか。日本にとっ重要な地域ですので、大きな関心をもちつづける必要があります。エルトゥールル号事件を風化させてはならないのです。
更に言えば、日本独自の中東関与と人間関係を築いておかなければなりません。旧来中東諸国の対日関心はアメリカとの関係で築かれていました。中東諸国にとって、新米とはなれないけど、アメリカに近いとされる日本とは堂々と付き合える。権力者に擦り寄りたいけど擦り寄ると周囲の友達から訝しく見られるけど、権力者の友達とは堂々と付き合っても訝しくは見られない。そんな対日関心でした。しかしその対日関心も最近は揺らいでいます。なぜならば、アメリカの存在感が薄らいでいるので、日本に擦り寄らなくてもアメリカに対峙できるようになったからです。
日本としては、中東の様々な国と積極的な人間関係を築いておくべきではないかと思っています。
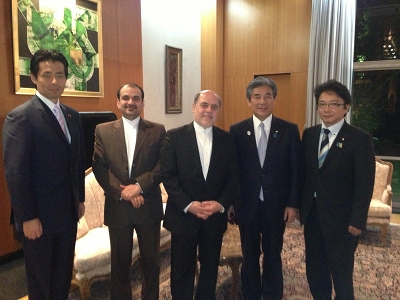
北方四島の一つ、国後島の対岸である羅臼の町に滞在しています。自民党政務調査会の領土に関する特命委員会の北方領土研修会に参加するためです。そして先ほど元島民もいらっしゃる羅臼の地元の皆様と懇談会に参加し、様々な話を聞いてまいりました。
終戦時点で北方領土には17000人ほどの日本人が住んでいたようですが、現在もロシア人が同じくらい住んでいるとのこと。そして、元島民の72%は北海道に、残り28%が道外に住んでいるとのこと。ちなみに香川県には14人の元島民がいらっしゃるそうです。
今まで国家戦略的視点でしか北方領土を見ていませんでしたが、先日の東京で参加した北方領土が返還要求大会に参加し、地元のご意見を拝聴してから、地元目線も大切だということに気づかされました。私が今回の企画に参加したいと思った理由です。仮に北方領土が返還されたとしても、現住のロシア人を追い出すことはできないから共存するしかない、そのときにどのようにしたらいいのか議論しなければならない。教科書に北方領土の記述が少ないため、北方領土の問題が存在することをしらない子供達がいることも問題だ(地元では副読本をつけているそうです)。北方領土を返還してもらうためには対岸の根室や羅臼などが発展しなければならない。などです。そうしたことは、地元にきてみないと感じないことなのかもしれません。
政策は会議で作るべきではない、政策は現場でつくるべきだ、と額賀委員長はおっしゃっておられましたが、実際にきてみて、その言葉の重みを噛み締めているところです。
動画コンテンツ「Ktaro CH(敬太郎チャンネル)」について、すこしコンテンツがたまってきましたので、一度ここでご紹介いたします。
お時間がありましたらお立ち寄りください。
アラブの春(アフリカの民主化革命)の波から暫く経ちましたが、相変わらず世界はシリア情勢に釘付けです。そして最近私はシリア情勢をはじめ、アフリカと中東情勢が気になってしかたがありません。
現在石油の9割を中東に依存している日本は中東の安定に相当の関心を持っていなければならないはずです。実はアメリカの中東依存度はそれほど高くなく、さらにシェールガス革命によって今後さらに中東への関心を低下させる可能性があります。それに加え、オバマ大統領は2期目に入っても相変わらず内政重視の姿勢を崩していないように見えますし、世界の自国の軍事配置をアジア方面にシフトすることをほのめかす発言をしています。アメリカの中東政策はイスラエルだけということになってしまうような気がしています。
911事件からアフガニスタンとイラクの戦争、そしてオサマ・ビン・ラディンの死を経て、国際テロ組織のアルカイダは中東からアフリカのサヘル地帯(サハラ砂漠南端一帯)に拡散しています。
一方で、数年前、チュニジアのジャスミン革命で始まったアラブの春はリビアなどに拡散しましたが、リビアはNATOの介入でカダフィは失脚・死亡しました。古代ローマの元老院議員の大カトーは演説の最後に必ずカルタゴ(現チュニジア)は滅ぼされるべきであると付け加えたと言われ、歴史的には後年にスキピオ・アフリカヌスによって完全に滅亡させられますが、チュニジアもリビアも独裁者の失脚でパワーバランスが崩れています。
それらの残党(革命派の中で新政権から疎んじられたグループ)が前出のアルカイダ系と繋がり、混乱を強めているように見えます。つまり、911以降の世界の中東政策によって何が起きたかというと、女王蜂を捕まえたら軍隊蟻が散らばったような状態で、如何にも収拾の付かない混乱が広がる可能性すら予感させる状況です。
今年はじめの痛ましいアルジェリア事件は、こうした混乱の氷山の一角に見えます。唯一、フランス(とイギリス)だけがこれに対処しようとしているように見えます。
事実、昨日、シリア情勢について、EUはシリアの反体制への武器のエンバーゴを解禁しました。これからフランスやイギリスは反体制派への武器供与を積極的に強め、混乱収集に力を注ぐことになると思います。時を同じくして、アメリカの共和党大統領候補にもなったジョン・マケイン上院議員は昨日、シリアを電撃訪問しています。これは、アメリカ政府をシリア介入に傾けるための工作だと思いますが、実際のオバマ政権は不介入を続けるでしょう。
原発再稼動の目処が立たない状況と、アベノミクスによる円安が進行する中で、益々中東情勢が気になります。そしてその中東情勢を揺るがしかねないサヘル地帯の残党勢力によるアフリカ情勢の緊迫も気になります。来月、アフリカ開発会議が始まりますが、投資だけではなく治安の面でも支援できる体制を整えなければならないと思います。
日本の成長を考えたときに、世界のモノ・ヒト・カネの流れの中心を取る、いわゆる空港や港湾のハブ化を進めることは絶対条件です。とは言っても、こんなことはもう随分前から言われ続けてきたことで、改めて言うこともないのですが、実はがっかりするくらい全然進んでいません。がっかりしたついでに、とりあえず、まだ取り返しの付きそうな航空政策について、ここで論じてみようと思います。
ハブ化に必要な要件は、当たり前ですが、モノ・ヒト・カネの流れで、メンタル面、コスト面、ベネフィット面での競争力があることです。まずは、私のブログ拙文「ルックコリア」ではありませんが、韓国の戦略を紹介します。韓国は海外のエネルギーを導入しなければ生き残れない外需依存度の高い国ですが、それだけ空港や港湾の戦略は大胆かつ良く練られているように見えます。
国際空港のインチョンですが、インチョン所在地を経済特区に位置づけ、外国企業に対して破格の税制優遇措置と、ビジネス・リビング両面でのベネフィットを都市計画として追求したいわゆるコンパクトシティーの実現を目指しています。同時に、先進諸外国とのビザ協定を結ぶなどの規制改革を行っています。つまり便利で安く行ってみたいと思う都市です。
で、現状はまだターミナル面積も小さいインチョンですが、既に数年前に成田の旅客数は抜かれています。成田に羽田を足すとまだ多いですが、数年で抜かれる勢いです。
それもそのはず、例えば諸外国では珍しい航空機燃料税や航空機の固定資産税という追加コストがある上、発着料や施設使用料も高く、しかも成田の場合はビジネスセンターである都心までタクシーで2万円以上もかかるというメンタル面のコストは、諸外国主要空港にはありません。
現在、欧州でもハブがドバイに取られつつあり、ドバイはアジアのエネルギーも吸い上げようと、中東主要4社で800機もの機材新規発注があるそうです。モノ・ヒト・カネの国際的な流れは大きく塗り替えられつつあります。
今は日本がハブ化の構想を打ち出し強く推進する最後の機会になるかもしれません。税制・規制なども含め、トータルとして航空政策を抜本的に改めないと、もうだれも日本に目を向けてくれなくなるかもしれません。