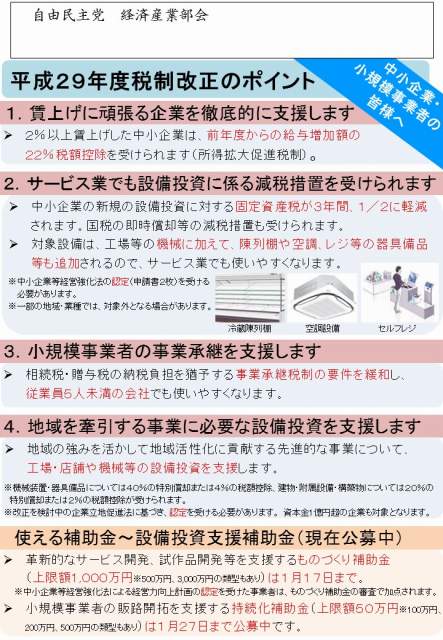来年度予算が衆議院で可決。年度内に成立するみこみとなりました。いよいよ個別法案の審議に移ります。
年始にご案内を申し上げましたが、第193回の通常国会は80以上の法案や条約の審議を行います。メディアで話題になるのは、与野党対決になりやすい働き方改革関連法案、組織的犯罪処罰法案、皇室典範ですが、多くの重要な法案の審議が予定されています。すでに党本部では賛成派、反対派、風見鶏派に分かれて審議が継続的に行われています。決して法案の重箱隅突き系で満足するつもりはありませんが、一つ一つ丁寧に議論をしていきたいと思っています。以下、審議の経過や私の思いは別に、その一部をご紹介させていただきます。
・医療介護分野/育児/労働分野
=(地域包括ケア・介護保険法)地域包括ケアシステムの強化を図ります。市町村の取り組みを後押しし高齢者が豊かな暮らしを送れる制度の構築、認知症施策の推進など介護保険制度改革、介護医療院の新設(介護と慢性期医療の双方の機能を持つ施設)、所得の高い介護施設利用者(340万円〜)の負担割合を2から3割に引き上げ(H30年〜)(上限あり)など。
=(医療ビッグデータ法案)予防も含めた医療全般や健康増進の手段にイノベーションを起こすため医療データの整備を行います。
=(精神障碍者福祉法)相模原障碍者施設殺傷事件を受けて、退院後の支援などの見直しを行います。
=雇用保険法)失業給付等の拡充、保険料の引き下げ(失業率低下のため)、育児休業期間の延長(保育所に入れなければ1年まで)、ハローワーク機能の強化などです。
・金融・中小企業分野
=(銀行法)銀行の口座情報を扱って民間が多様でアイディア豊かな事業を行えるようにすることで、利用者の利便性を向上させます。
=(中小企業信用保険法)銀行が過度に信用保証制度に依存することなく責任をもって金融仲介業務を行えるようにし、中小企業小規模事業者にとっては今まで以上に頼れる銀行となるための制度改正です。セーフティーネットも手厚くなります。
・給付型奨学金制度の創設
=(日本学生支援機構法)学生への奨学金について、日本学生支援機構法を改正し、一定の条件で月額2〜4万円、社会的用語が必要な学生には入学時24万円を支給する制度を新設します。
・電気通信分野
=(電波法)3年ごとに改定される電波利用料について、携帯電話は現行の1局200円から140円になります。
・農林水産分野
=(農業競争力強化支援法案)生産者の所得を改善するために資材価格や流通のメカニズムを刷新する法律案です。国や地方自治体の役割を明確にし、民間事業者の参入を促進し、資材や流通において合理的で国際競争力のある価格形成を促します。
=(土地改良法)農地バンクが借り入れている農地について、農業者からの申請によらず、都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施できる制度を設けます。ため池整備なども農業者の申請によらず国または地方公共団体が同意を求めず実施できるようになります。土地改良事業の申請人数要件を廃止します。
=(農村地域工業等導入促進法)工業誘致に限定せずサービス業にも拡大します。ちなみに支援内容は、たとえば農地転用の特例、農振法の農用地区域からの除外、個人が譲渡した場合は所得税の軽減措置、低利融資の利用などがあります。
=(農業機械化促進法)時代にマッチしなくなった評判の悪い同法(農機具の開発や所有について箸の上げ下げを指示する法律)を廃止します。
・住宅・不動産分野
=(住宅セーフティネット法)高齢者や子育て世帯など、住宅を確保する際に国の配慮が必要とされる方々のために、空き家などの利用して住宅セーフティーネット機能を強化する制度を強化します。
=(不動産特定共同事業法)空き家などを再生利活用する事業に不動産業者が幅広く参入できるよう同事業の特例を設けたり、流行りのクラウドファンドによる資金調達を可能にしたり、約款規制を廃止するなど規制緩和で、優良不動産ストックを形成・流動化させ、地方創生や観光に役立たせるための制度改正です。
・その他
=児童虐待への対処、悪質な民泊業者の排除、受動喫煙防止、安全保障上機微技術の海外流出防止などの審議を予定しているほか、民法改正も検討中です。