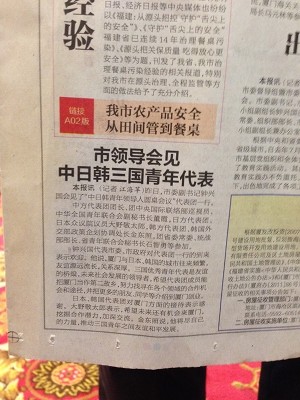先週末、日銀の黒田総裁が一段の金融緩和を発表しました。通常は緩和観測が流れた後に実際の発表されることが多いので、私自身、突然の緩和発表は大変驚きでした。と言うのは、金融政策も市場との対話が重要だからです。特に政策決定会合の結果にも現れるような意見が割れる決定の場合はもう少し丁寧に行う必要もあると思います。ただ中身は反対ではありません。なぜならば、何もしないリスクより、するリスクを積極的にとるべきだと思うからです。
この日は丁度、GPIFの運用比率の見直しの発表やら予算の話があったりで、株式市場としては大物の好材料が並んだため、当然のごとく大幅上昇しました。
今日はこのことを、日本の経済と消費税とを絡めて考えてみたいと思います。
まず景気と消費税についてです。消費税増税判断は実施するにせよ延期するにせよきわめて難しい問題ですが、私は消費税の判断は実施を前提すべきであるけど、純粋に経済の動向を見て判断すべきであると思っています。
景気状況を見ると、第一四半期に対前期の実質の年率換算で+6.7%、第二四半期でー7.1%となり、第三四半期でどうなるのかということが大きく話題になっています。今月17日には、第一速報値が発表され、12月8日に第二次速報値が発表されると思いますので、正確にはそれを待たなければなりませんが、確かに当初予定の4%という成長は困難なようです。
第三四半期の成長鈍化はほとんどが天候要因だということが民間の予測のようですが、景気動向指数は悪化には転じているわけではなく、設備投資も先行指標の機械受注額も+5.7%と十分ではないものの悪くない。大きな問題は消費。CPIはマイナスが続いています。そういう意味では、結局デフレ脱却、というかデフレマインドの脱却がまだ本調子ではないということになります。
これからの成長戦略の実行には構造改革などが伴うため、できれば成長率は1%程度は欲しいところですが、詳細は省略しますが、実際には0.5%程度になることが予想されています。この0.5%というのが消費税判断の境目になるはずです。0.7〜1%程度以上であれば増税、0〜0.3程度では延期、中間は悩む。結局は政治判断ですが。ただ、中途半端な延期は政治的な空白を生む可能性もあり、それ自体が成長戦略の実行に障害となる可能性も秘めていますので、極めて高度な政治判断になると思います。
次に金融政策についてですが、現在の状況では外需や公共事業には頼れない状況であることは間違いない。そうすると一段の金融政策ということになるわけですが、これも実体経済にどのような影響がでるのか定かではありません。
今回の日銀の決定は、
1、マネタリーベースの拡大 年間60兆円→80兆円
2、長期国債保有残高 年間50兆円→80兆円
3、ETF買い入れ金額増加 年間1兆円→3兆円
4、REIT買い入れ金額増加 年間300億円→900億円
ということですが、GPIFの国内株式比率12%→25%などと併せて、株式相場は急伸した。一方で円安も一段と進行することになります。もちろんETFやREITは直接的ですので、効果ありありですが、円安が進行すると言っても輸出企業が大きく儲けるかというと、原材料やエネルギーコストなどでそうでもない。
問題は、だからと言って金融緩和は駄目だということにはならないということです。なぜならば、このままではデフレマインドが続くからです。ただし、米国も金融の量的緩和を終了させました。長期的な出口の戦略は必ず練っておかなければならないと考えています。