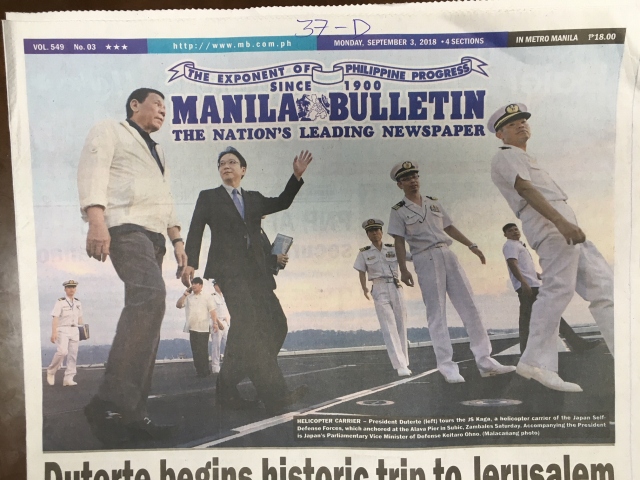(中国共産党対外連絡部宋濤部長)
先々週、中国を訪問しました。その時に思ったことを、徒然なるままに書き残しておきたいと思います。
中国は鄧小平以来の改革開放によって独自の発展モデルを作り上げ、目覚ましい経済発展を遂げていますが、軍事費の増大や急進的な海外戦略によって諸外国との軋轢を生んでいます。一方で、先進国では経済グローバル化の進展とともに低所得者層の所得が伸びなやみ、格差の拡大を通じて排他的ムーブメントが増大し、国際政治の不安定化の原因になっています。こうした異なる発展モデル同士の争いが顕著になるのであれば、今後はグローバル化が見直され、国家若しくは経済ブロックの役割が高まり、サプライチェーンは再調整される可能性があります。この国際社会の動きは、19世紀から20世紀にかけてのパワーコンフリクトを彷彿させるものがあります。もちろん要因やタイミングや規模の面では全く異なりますが、戦前の失敗を繰り返さないために、人類は努力を重ねなければなりません。
エレファント・カーブ(像の鼻)という有名なグラフがあります。所得階層ごとの過去30年の所得の伸びを示している図で、横軸は所得分位(左が貧しく右は金持ち)、縦軸は30年間の所得の伸びになります。そうすると、まるで象の鼻のようなグラフができあがり、名前の由来になっています。左から新興国低所得層は20%程度(象の尻)、新興国中間層は80%程度(象の背中)となり、先進国内の中間層は0%程度(象の鼻の付け根)、先進国高所得者は60%(像の鼻の先)となります。
つまり、新興国の低所得者層に位置する人たちも、確実に賃金は上がっているのに、先進国の中間層のみが賃金が上がらず、世界の中で唯一割を食った結果となっていて、その結果、民主主義国家である先進国で政治が不安定化しているということになります。中国でも近年の急速な経済発展によって格差問題が顕在化していますが、その低所得者層でも、賃金は伸びていて、確実に生活レベルは改善しているということになるのだと思います。
経済が発展し、国が豊かになると、民主化が進む、というのは通説ですが、別の発展モデルを可能にしているのは、ネットテクノロジーなのだと思います。私は現代版グーテンベルグだと思っていまして、後述するように民主化と同規模の社会的変化をもたらしています。さらに言えば、ネットテクノロジーによるイノベーションと中国のような覇権政党制というのは、相性が極めて良いことも指摘されています(例えばシェアリングエコノミーをやろうとすると、日本では分野によっては利害調整という膨大な政治コストがかかりますが、中国では、やろう、の一言で済む)。
もちろん、だからと言って中国型覇権政党制がよいなどということは毛頭ないわけですが、イノベーション力を高めるためにはテクノロジーの社会実装が必ず必要になるわけで、その意味では、日本も政治の決断力もさることながら国民全員の意識変化も必要になるのだと思います。
一方で、恐らく中国共産党の最も恐れていることは、格差による政治の不安定化です。著しい成長を遂げたと言っても、未だに格差が存在するのは事実で、内陸部や中西部は未だに豊かではない。だからこそ、仕事を作り、社会保障制度を作り、発展モデル都市を作り、ということを中国政府は懸命にやっていて格差是正に努めている。結果的にそのひずみが海外戦略に表れていて、諸外国からの批判に繋がっている様に見えます。このあたりの件は、丁度2年前くらいに記事にしているので、ご興味があればご高覧ください。https://keitaro-ohno.com/3405
さて、今回、中国を訪問したのは2年ぶりとなります。中国には、同期の同志と共に毎年訪問する努力をしており、毎回北京に入った後、地方を訪問することにしています。今回は、北京と深セン。訪問を始めた2013年当時は関係が冷え込んでいたので、話が全く噛み合わないことの連続でしたが、今回の訪問は、極一部で安保関係の話になった時以外は、終始柔らかい雰囲気に終始しました。たまたま訪問したのが、前述した鄧小平による改革開放の40周年にあたる12月18日を挟んでのものとなったのも理由の一つなのかもしれません。実は日本が防衛大綱を閣議決定した日でもあり、中国政府は懸念を示していましたが、現地ではその報道よりも改革開放の報道が圧倒的に多かったと思います。いずれによせ、今年の日中関係はかつてないほど好転しています。今年が丁度、日中平和条約締結40周年、日中国交正常化45周年の節目に当たる年だから日中関係が改善したのだ、ということではなく、もちろん周年行事というのは極めて重要ですが、背景には後述する米中貿易戦争などと報道される国際政治が大きく影響しているのだと思います。
訪問の目的は終始一貫しています。中長期的な視点で健全な日中関係を構築すること。日中関係が論じられるとき、中国は政治的にも経済的にも国際社会の中で主要なアクターであって重要な隣国である、とよく説明されますが、それは決して大国になりつつあるし隣国だから仲良くしなければならない、ということではなく、本来は、国際秩序の維持のために日中関係がどのような関係を構築しておくべきなのか、という事が主眼であるべきです。であれば、日本の立場を主張することは重要ですが、言い「たい」ことを言えば良い、のではなく、何をどうするのかを考えた上で、言う「べき」ことを言う事こそが重要なのだと思います。
ファーウェイ問題。訪問中、中国側からファーウェイ問題の話題提供が何回かあり、気にしていることはよくわかりました。事の発端は、米国が中国企業ファーウェイに対して調達上の事実上の排除勧告を出したことで、米側の主張は、同社製品にいわゆるバックドアが埋め込まれており、同製品を通る情報は、中国側に漏洩される可能性があるというもの。随分前から指摘されていた問題です。
課題は2つ。1つめは、事の本質が、米中のサイバーセキュリティ(サイバー攻撃)の概念が全く異なるということ。これも先にご紹介した記事に書いていますが、自国の安全保障上ならいいと考える国と、安全保障のみならず経済産業上のものもやってしまえと考える国との差であると指摘されています。このことについて、国際社会はルールを明確に確立し透明性を確保していかなければならないのだと思います。2つめは、個別的な対処の話。少し専門的な話になりますが、米側が主張するバックドアの証拠は公表されていません。つまり、証拠はない。ハードウェア上設置すると確実な証拠になりますから、あるとすればソフトウェア上の話。であれば、全世界にどれだけ散らばっていたとしてもリモートでも消そうと思えば消せる。また、国家安保上、中国政府が求めればファーウェイ社は情報を提供する義務が課せられている、という外形的な問題も指摘されています。つまり、真実はよく分からない。疑念が生じているのであれば、個別的な問題としてWTOで議論をすべきだと思っています。
訪問直前に、我が日本政府が、政府調達においてサイバーセキュリティ上適切なものしか扱わない、という指針を示しましたが、メディア上では米国のファーウェイ問題と絡めて論じられることが多かったと思います。政府方針は、全く瑕疵のない内容で、不適切な製品は調達しませんよ、というだけの話。しかし、発表の時期が問題を大きくした。なぜわざわざファーウェイ問題が表面化した直後に発表するのか。少しずらしてもよかったのではないかと思っています。
米中貿易戦争。ビジネスのサプライチェーンが複雑に絡み合っている現代において、関税を引き上げたり引き下げたりすることによって、自国が有利になるかどうかは、短期的な意味においても単純には分からないはず。分かっていることは、間違いなく世界経済に負の影響を及ぼすということです。
ただ、冒頭申し上げた通り、そもそも先進国内の格差問題の歪が、こうした恫喝外交に帰着していると考えれば、解決する方針は2つしかなく、1つは先進国内の格差問題を、他国にはまねできないような活躍の場を中間層に提供する形で解消していくこと、もう1つは世界の自由貿易の質を、1国独自主張ということではなく、これもWTOの範囲内で調整していくこと、なのだと思います。私自身は、本来、前者の形で、各国が努力をするべき問題であると考えています。
豊かさと倫理観。昔の報道で、中国の路上でひき逃げされた被害者が、大勢の通行人から無視されていることが非難されている、というのがありましたが、一方で、中国の豊かな地域では、例えば電車に乗ると必ず高齢者や妊婦さんに席を譲るなどの道徳倫理観の高い場面に遭遇します。政治思想にも絡む話ですが、人間というものは、物質的豊かさを手に入れれば、精神的豊かさを求めるようになるのか、考えさせられます。中国でも最近、古典を読むことが流行っていると聞きます。
キャッシュレス。今回の訪問では、北京と深センだけでしたが、どちらもキャッシュレス。現金を持ち歩く人は殆どおらず、店舗では現金お断りのところもあり、ごく最近、中国人民銀行(中央銀行)が、国家の公式決済手段である現金が使えないのはダメだ、と現金お断り禁止令を出したとか。日本では、現金決済が9割と言われていて、政府主導でキャッシュレス誘導をしようとしていますが、本来、民間主導で利便性が高まる決済手段が広まらないところに日本のかかえる問題を感じます。
一方で、中国のキャッシュレスは、個人間の送金手段など幅広い使われ方をしていますが、そのやり取りにおいて個人の信用力がサイバー空間上で格付けされる仕組みになっていて、その信用力によってより良いサービスを享受できるシステムになっているらしく、普段の市民生活でも、善良な市民であることがメリットを享受できる前提になっているとのこと。儒教だ古典だ、道徳だ倫理だ、と言わなくても、善良でなければ生きづらくなっているのであれば、それはそれでとても良い事なのかもしれません。
表面が変わっただけではダメだと思う人もいるかもしれませんが、考えてみれば、日本でも、見られてなければ平気でゴミをポイ捨てするなど、他者という相対的評価を行動基準にしている人がいますが、監視カメラが至るところに設置されて誰もポイ捨てしなくなったとして、いやそれは相対基準だから倫理という絶対基準じゃなければダメだ、と思う人がいてもおかしくはありませんが、ダメなわけではないと思っています。
しかしそれでも中国の内陸部など農村の現状はまだまだ厳しいものなのだと思います。13億人のうち6割以上が農民で、平均所得が1/3程度。農村地域から都市部に出稼ぎに出る人が3億人程度いるとのことですが、それでも必ず都市部でよい稼ぎができるわけではなく失業も多いのだとか。いわゆる農民工問題です。深センのとある方が、移民、と表現していたのがとても印象的でした。さらに、最近、社会保障制度を改善し、公務員だけが対象だったものを国民全員に広げたそうですが、戸籍は簡単に移せないようで、そうした人たちの社会保障サービスは真正住民とくらべると低いとのこと。
いずれにせよ、中国が人口減少を迎えるのは2040年程度。1人っ子政策を廃止したとはいえ、すぐに流れが変わる物でもないと思います。その時までに、農民工や移民の問題が解決されていなかったとしたら、または中間層が生活レベルの改善を実感できないほどある程度豊かになったとしたら、中国の対外活動はどのようなものになるのか、今から考えておく必要があると思っています。