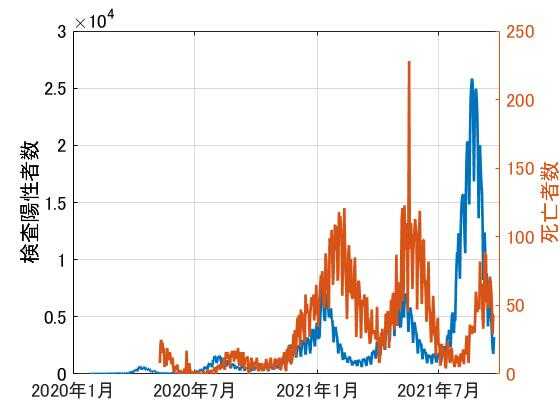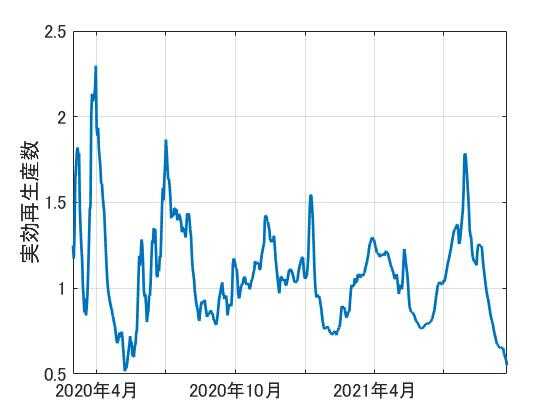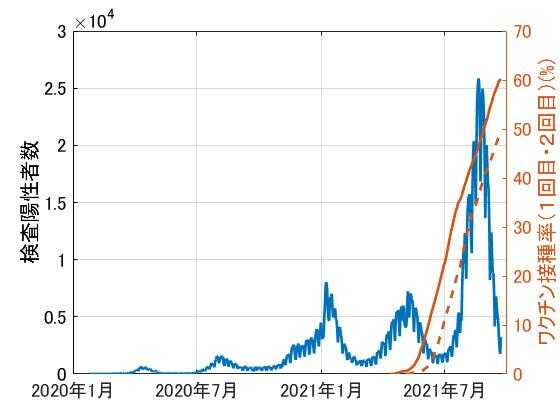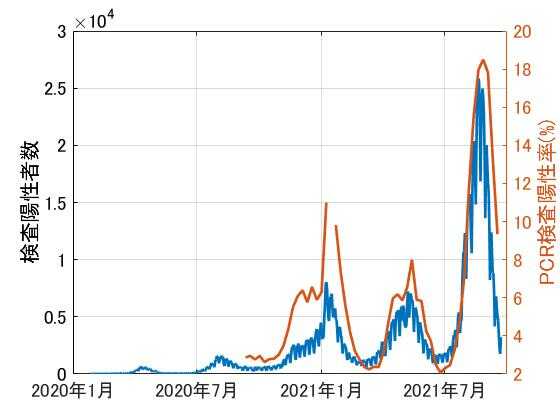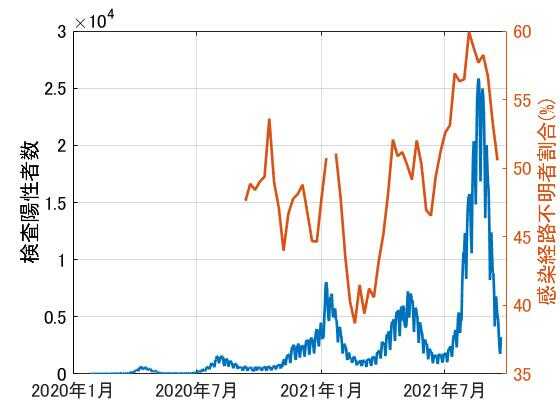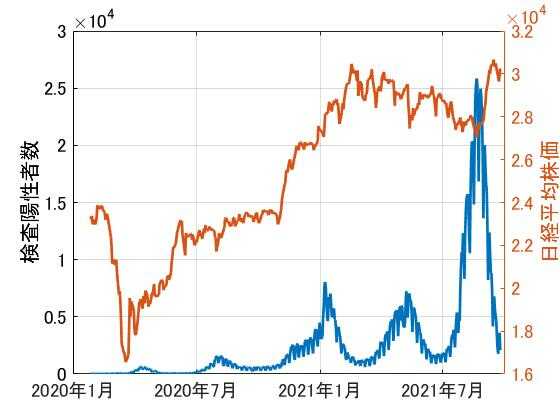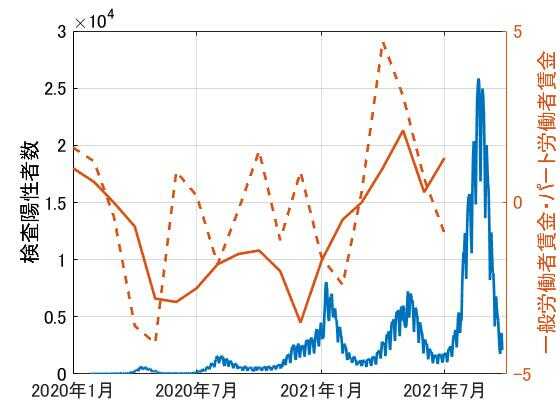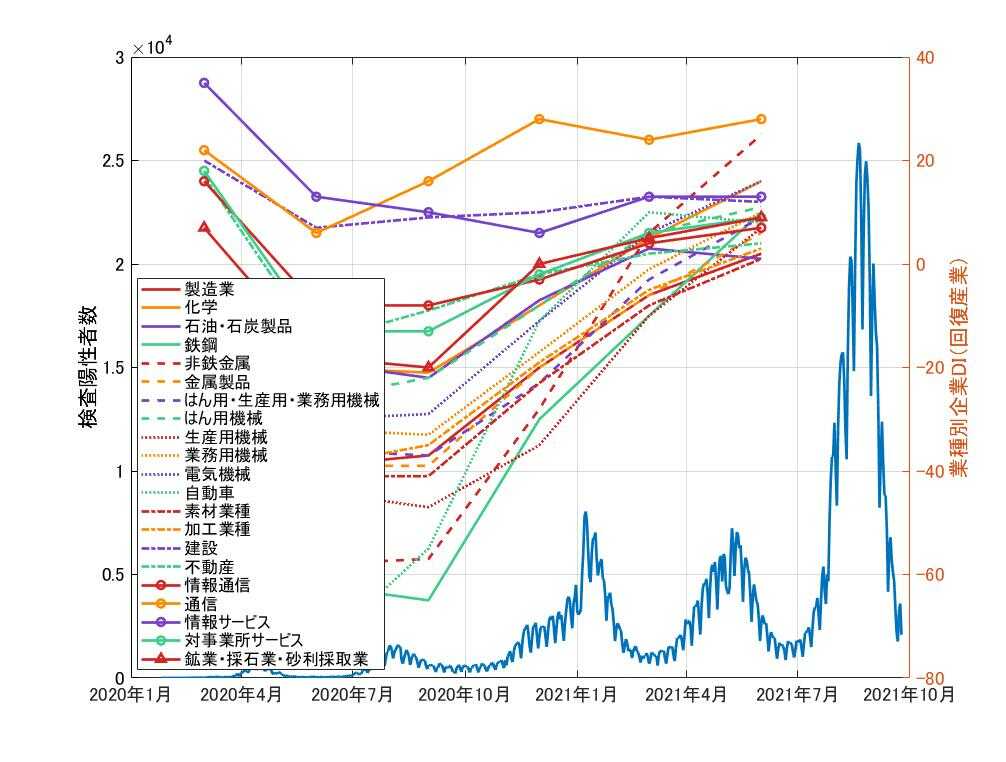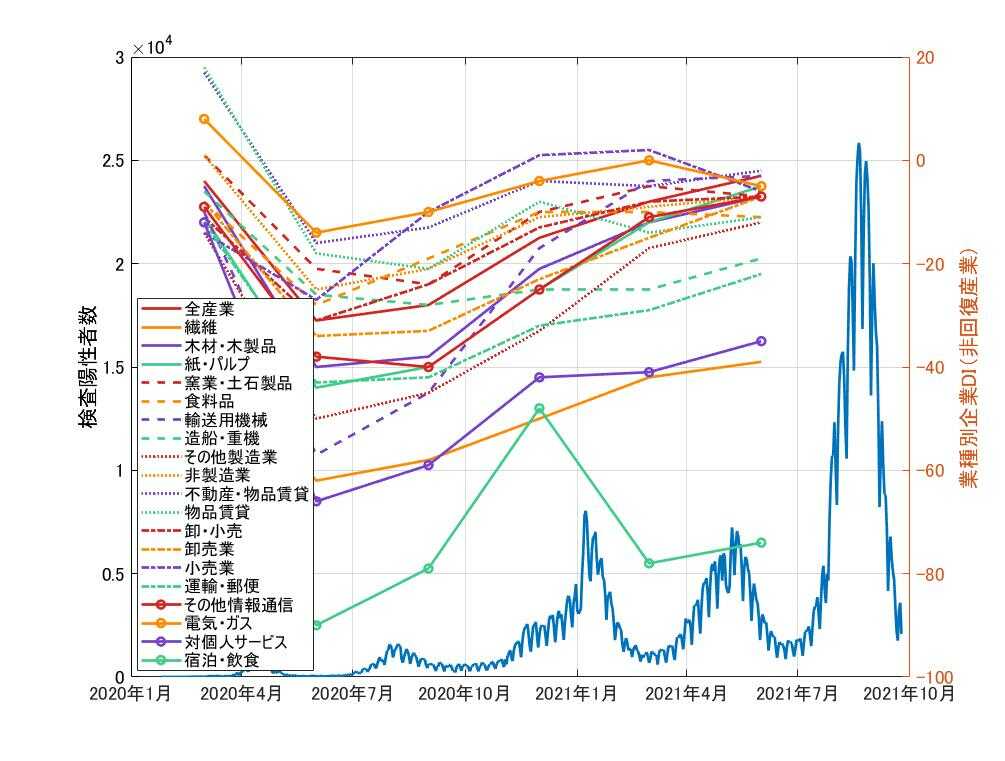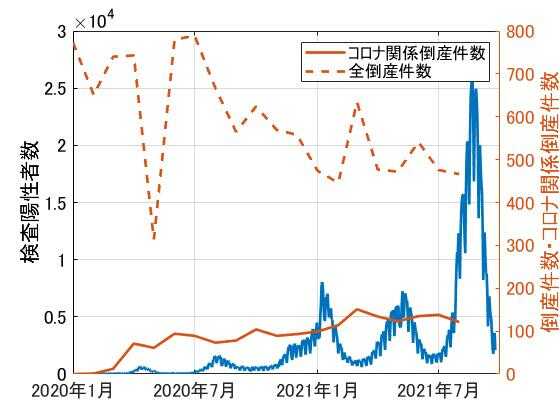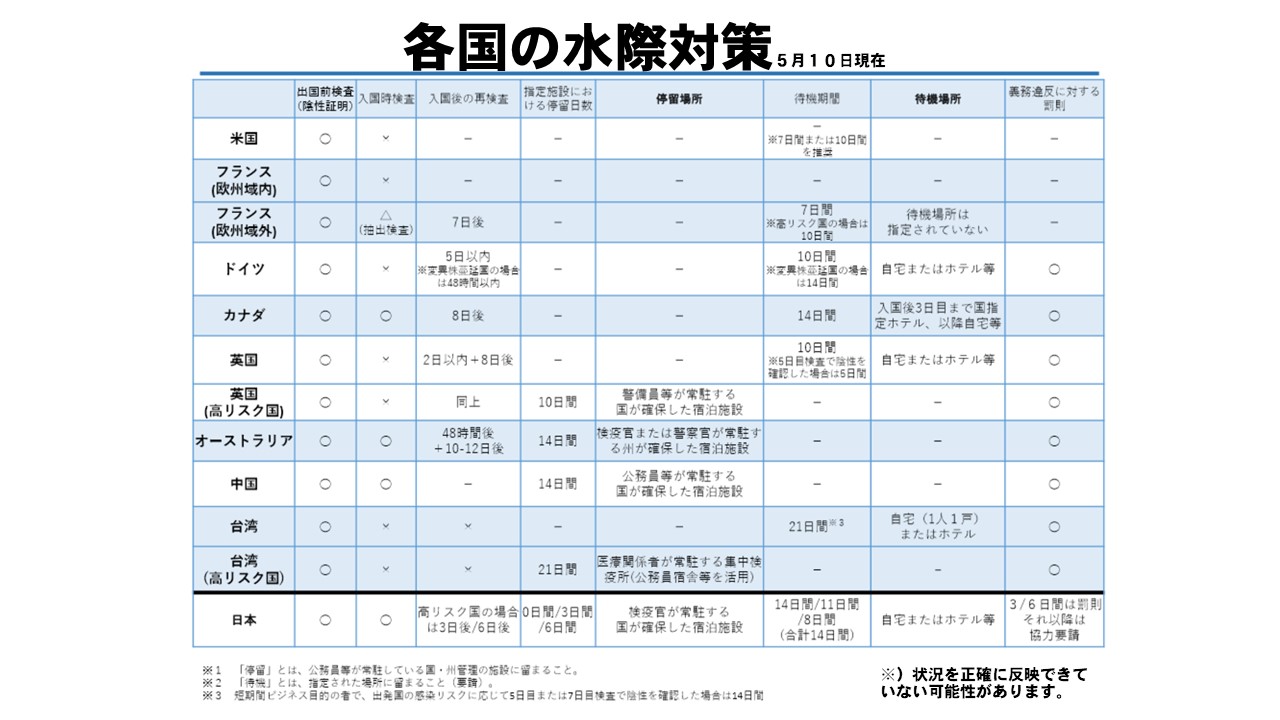いよいよ明日、自民党総裁選が告示されます。これから本格的な政策論争が始まります。どなたが次期総理にふさわしいか。党員の皆さまには特に注目頂き思う方に投票を、また党員以外の皆さまも政策を聞いて日本のあるべき姿を共に考えられる機会になればと思います。現在4人が立候補されています。岸田文雄さん、河野太郎さん、高市早苗さん、野田聖子さんです。今回の総裁選では、私は岸田文雄さんに日本の未来を託すことに決めました。
それに先立って、書き記しておきたいと思います。前回も書きましたが、約1か月前、総裁選の実施時期を巡ってかなり分かり難い政局となりました。初当選以来、これまで厳しい政局となることは幾度かありましたが、それらとは決定的に質の異なるものでした。ズバリ言えば、有権者や党員の皆さまに対して、説明ができたかどうかです。過去の政局は、全てとは言いませんが、自分なりの理解をし、中身の説明をし、自分の意見を述べることができた。今回は、全くできなかった。
それまで菅総理は仕事では最善を尽くして確実に結果を出してました。しかし、この総裁選や解散時期をめぐった政局については、メディアは揃って四方八方からダメ出し。政治は完全に国民の信頼を失っていました。この状態で、もし、菅総理が総裁選に出たとして派閥談合で再任されたら、間違いなく皆さんは国民不在だと感じたと思います。
菅総理がだめだということではなくて、我々政治がだめだと思われたところがだめなので、そういう場合は、組織の透明性とガバナンスがモノを言うはずです。等身大の政治の姿を皆さんの前に晒して評価いただく。これが信頼回復の最大の手段になるはずです。そのためには、派閥一任の解消と開かれた総裁選を求めることが必要だった。本来、自浄作用としてこうしたことが自然に起こるのが望ましい。しかし、起きなかったことに危機感を感じたからこそ自らの手で実行した。それが福田達夫さんであり党風一新の会でした。
ここを起点にして中堅若手で党改革を訴える「党風一新の会」ができたことは既に前回書きました。打ち出したのが、今回の総裁選では派閥一任を解消して自由投票とし、国民や党員の皆さまと一緒に考え国を形作れるよう、開かれた総裁選にすることです。ところが残念だったのがレッテル貼り。この会を、特定の候補者を支持するための会だとか、選挙基盤が弱くて派閥領袖に従ったという理由だけでは選挙を戦えないから自由にしろと言っている圧力団体だとか。この薄っぺらいレッテル貼りには私は耐えれない。
そもそもこの会は何を目指しているのか。派閥一任回避と自由投票を求めたのは目的ではありません。まして、特定の候補者を支持するための母体でもなく(もしそうだったら新しい派閥ができただけで我々の主張と根本的に矛盾する)、派閥の存在自体を直ちに否定しているわけでもなく(否定するのであれば新たな根本的ガバナンス体制を直ちに構築すべき)、主目的は、一時の党勢凋落という事態に陥ったのは党のガバナンスが脆弱なことが原因だという認識の下、党改革とその先の国会改革、そして統治機構改革と、それを通じた「政治は国民のもの」という原点を目指しているものです。
国民からの密室長老政治というレッテル(実態は少し違います)に対する不信感と実態のギャップを埋めるための行動をとったもので、我々が本質的に目指しているのは、国民の意識をしっかり掴み、やるべき行動を生み出す自浄作用の仕組みです。すなわち個別の状況を把握し、やるべき行動を提示し実行する仕組みです。オカシイと思われないよう常に自己チェックができる体制や制度などのメカニズム、仮にオカシイと思われるなら分析し評価し改善するという行動につなげていく仕組みです。これが我々の言うガバナンスであって、それを通じて、党運営を近代化し、政治や自民党と国民や党員の距離を近づけ、前向きな政策論議が巷で行われるような土壌を築くべきだ、という視点に立っています。
では具体的にガバナンス強化とは何を言っているのか。
第一に、意思決定過程の透明化と原則主義の強化です。一言で言えば説明責任。冒頭書きましたが、難しい政局でも説明可能にしていかねばなりません。そして少なくとも事前に原則を打ち立てておき、それに従えないか逸脱するようなことが生じたら必ず説明する、というのが私の言う原則主義です。政治は信頼が根本だと考えています。政策は対立する可能性はありますが、なぜそういう結論になったのかを説明すれば、納得は頂けはしないかもしれないけど理解はしていただけるはずで、それが信頼に繋がっていくのだと思います。人事も資金も原則主義を強化すべきです。岸田さんは、党ガバナンスコードを主張しました。まさに原則主義の考え方です。
第二に、パブリックリレーション(PR)戦略です。PRというと、何となくアピールに聞こえるかもしれませんが、本来的な意味では、国民との関係(リレーション)をどのように構築するかという戦略です。大切なのが、国民からのフィードバックをどのように取り入れて対話(コミュニケーション)するかです。これには2つの方向があります。ネガティブな事象を扱う場合とポジティブな事象を扱う場合です。前者の典型例が緊急事態の際のリスクコミュニケーションです。その為には、リスクをマネージメントする機能が不可欠です。後者は、アジテーションや扇動にならないような仕組みをどのように構築するかです。そして両者に共通で必要なのが、インテリジェンス機能です。PR戦略部門が描く戦略に基づいて必要な情報を権限を持って収集できる体制が必須です。単に各部署から上がってくる情報を垂れ流す、平べったいPRにならないようにすることです(政府の広報担当部局はほとんどがこの類です)。国民や党員の意見を収集し党運営にフィードバックし政治の運営を改善していく。先に書いた党風一新の会の一歩目の部分です。
第三に、正統性と正当性の明確な役割分担に認識です。正統性とは民主的に皆で決めたという正しさで、政治が担います。正当性はとは、学術的若しくは論理的な正しさで、主に学者や行政などが担います。社会問題が複雑多様化しているため、政治判断だけでも、あるいは学術的・論理的正しさだけでも判断が付かない問題が多くなっており、EBPM(根拠に基づいた政策立案)と言われるように両者を融合させて政策を運用していく重要性が益々高まっています。しかし、その両者の役割分担を明確に意識しなければ、安定的運用は不可能です。例えば、学術界の中でも意見が割れるような複雑な問題の場合、学術界も民意に流されたりすることもあるはずです。また、行政組織も、大臣という政治家の上司がいるのでどうしても大臣の意向を尊重することになります。その境目と役割を相互に明確に認識するためのツールを準備しなければなりません。
第四に、意思決定における演繹性と帰納性の担保です。小難しく書きましたが、要は国民の意見を吸い上げてボトムアップで政策を実行することもあれば、国家戦略上の観点から総理総裁がトップダウンで政策を実行することもある。一方で、時間軸の中で、将来のある時点での理想的な国の在り方を定めて現在実行すべき政策を立案することもあれば、現時点での直面する課題を解決するために政策を立案することもある。いわば空間軸と時間軸のなかで、どのように政策を組み立てていくのかという基本的な概念を国民の皆様と共有しておかなければならないのだと思います。その中で、地方組織の在り方や国家戦略の在り方が定まってくるのだと思います。
第五に、政調の政治的機能強化です。政調は政策を作っていればよいわけではなく、政策の位置づけを俯瞰的に見て実行していかねばならず、その為には政治力を強化していく必要があります。これまで政調会長の属人的能力でカバーされてきましたが、それを補うために制度として担保していくべきです。例えば国会対策委員会と連携して議員立法審議優先権を獲得し、政府がやらないのであれば立法府として与党が議員立法を成立させやすい環境を整えること、税制や予算の社会的インパクト・財源を総合的かつ精緻に分析・評価・立案ができるインテリジェンスを併せた機能、その為に必要な情報にアクセスする権限とクリアランス制度、などが考えられます。
第六に、派閥の機能です。前述しましたが、無派閥である私が言うのも変ですが、現時点においては、派閥は党ガバナンス上、一定の役割を担っていると認識しています。政治はまとめるのが仕事ですので、300人も国会議員がいてそれぞれがバラバラな意見を言い続けていたら纏まりません。引き出しに間仕切りがあるように、ある程度のグルーピングは自然なことだと思います。逆に言えば、総理にしたいと思う人の周りに人は集まっていくのが人間の本質ですし自然なことです。また情と理のバランスをここで取ることを否定すれば情のない政治になります。問題の本質は、派閥の運用が説明不可能なときです。とにかく俺の言うことを聞け的な運用は、政局安定期は問題ありませんが、不安定期には混乱に陥りやすい。従って、派閥の運用も、派閥ガバナンスコード的な原則主義が必要なのだと思います。一方で、未来永劫このままでいくべきなのかは別問題です。それを超える高いレベルのガバナンスが得られるのであれば、移行することも選択肢だと思います。問題はそれがどのようなものかを見つけられていない事です。
第七に、政府(官邸)と与党(自民党)との役割分担です。安倍政権で官邸機能が強化されたのは皆様もご存じの通りだと思います。これは絶対的に正しい方向ですが8合目に到達できたところなのであと2合昇らなければなりません。国家ガバナンスの更なる強化です。ここはまた深い議論があるので別稿に譲りますが、一方で、自民党の役割が低下しすぎた。単純に党の役割を強化すると、多様な意見が噴出し、いわゆる決められない政治や非合理な政治になりかねない。そうならないためにも、党ガバナンス強化を前提として、党の機能や権限の強化が必要になってきます。
追伸(9月21日)
党風一新の会による総裁候補者との意見交換会を実施しました。まずは事務段取りを完璧にこなし、当日は見事な司会進行を務めた同期、田畑さんに心から感謝とエールを送りたいと思います。
今、政治が直ちになすべきは経済対策を含むコロナ対応などの政策ですが、それらは既に他の公開討論会で議論され深掘りされているため、この会では政策については敢えて触れず、むしろ政策を実行するやり方や仕組みを中心に議論いたしました。まさに党改革や国会改革(本質的には統治機構改革)です。
https://www.news24.jp/articles/2021/09/21/04943136.html
https://www.youtube.com/watch?v=mmwuW40gQSU