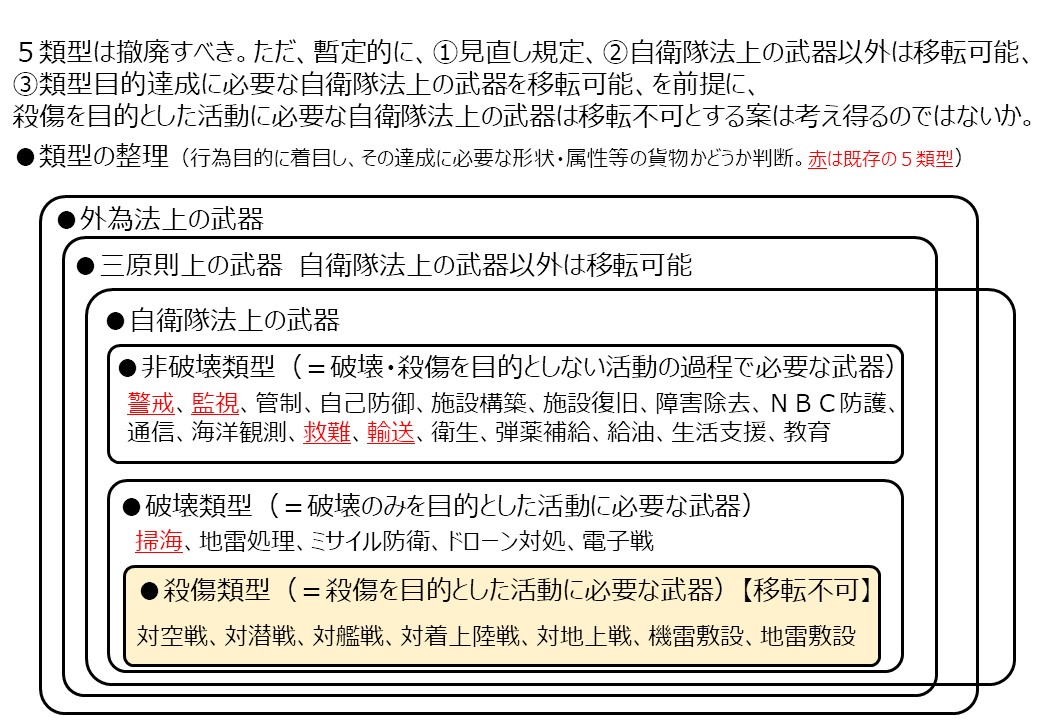一般論として、組織に不祥事が起きたとき、組織の全員が悪いわけではないのだとしても、俺は悪くない、などと毛頭でも思うような人がいたら、恐らくその組織に未来はないのであって、申し訳ない、二度と起こさない、と心から思うことから始まらないと、再生はできないのだと思います。
政治改革の嵐が吹く政界に身を置きつつ、今国会終盤の最大の焦点となった政治資金規正法改正が、大難産かつ異例のプロセスで何とか成立しました。審議を担った政治改革特別委員会で与野党協議の責任を預かるものとして、成立に至ったことについては安堵しておりますが、極めて後味の悪いものになりました。
今回は、その雑感を書き記しておきたいと思います。
■政治資金規正法はザル法なのか
注目の的となったのは、政治資金規正法と呼ばれる、我々政治家の政治資金の収支の公開を定めている法律で、この法律は、以前からザル法と呼ばれます。なぜか。
政治資金規正法は、規制法とは書きません。規制は制限するものですが、規正は正すものです。即ち、この法律の目的・理念は、政治資金の収支の公開を通じて、政治活動が国民の不断の監視と批判に晒されることで、政治活動が国民監視の下で正されることを期待したものです。従って、収支報告書が正しく書かれなければ意味がないので、記載については厳しい罰則がかけられている、というのが基本的な構造です。(資金が贈収賄や選挙買収に使われたら、それはこの法律で罰されるわけではなく、公職選挙法とか刑法によって裁かれます。)
しかし、この政治資金規正法は、過去に度重なる不正によって、問題が起きるたびに、規正ではなく規制となる改正条項が追加されてきました。今回の事件は、政治資金の不記載・虚偽記入ですから、法改正をするまでもなく政治資金規正法違反ですが、その発生原因を防ぐために再度改正されたものです。発生原因は、不正の温床となる現金管理を許容していたこと、代表者の会計責任者に対する監督責任が不明瞭であったこと、収入に対する第三者による監査が不要であったこと、であったので、現金管理禁止と監査対象拡大による監査実効性強化、及び代表者の監督責任強化を、実質的な再発防止策として規定しました。
ただ、それ以外の、未だ問題が生じたことがない部分は、規制されているわけではなく、単に規正を理念とした公開が担保されているだけです。すなわち、構造的には、規正を理念としている法律の上に、問題が起きたところだけ規制を理念とする条項を積み重ねているため、規制の概念でこの法律を見れば、ザル法に見えるということなのだと思います。
例えば、政治資金の事業収入で言えば、規制されているのは政治資金パーティーですが、それ以外にも機関紙発行による収益もあります。1部月3000円くらいだとすると、2部で年間5万円を超えます。しかしこれには全く規制はかかっていません。穴と言えば穴です。そうした個別対処ではもはや問題を解決できないのかもしれません。むしろ政策への不正な影響を排除することが政治資金の収入の大きな課題ですから、政党助成金や献金も併せて、収入全体構造を適切にバランスよく制限していく方が理にかなっているように思います。
規正法で守られるのは民主主義です。規正法の考え方は、法律にも書かれている通り、政治資金が健全な民主主義の発展を希求して拠出される国民の浄財であるので、この法律は国民の自発的意思を抑制しないよう適切に運用しなければならないのであって、だからこそ政治団体はその責任を自覚して疑念を招かないよう努めなければならないわけです。しかし今後、政治資金に関する不正が続き、政治不信が絶えないのであれば、むしろ健全な民主主義であるはずの政治に拠出する浄財さえなくなるはずなので、いっそのこと原則と根本理念を規制法にしてしまうことも考えうるのだと思います。
■いわゆる連座制はザルなのか
今回、政界で最も問題視されたのが、秘書がやった、知らなかった、という政治家の言い逃れです。会計責任者である秘書だけが処罰されて政治家が何の処罰もされないのは理不尽ではないかということです。そして我々政治家側も、もう二度とこうした言い逃れを許さない、許してしまうと二度と信頼をお寄せいただけなくなる、そういう強い思いの下で改正に取り組みました。
そのなかで、連座制という言葉がもてはやされましたが、実は連座は近代刑法では明確に否定されます。封建時代の村社会で成り立っていた概念で、現代では責任主義のもと、責任がなければ処罰はありません。比較されるのが公職選挙法ですが、この法律では選挙違反があった場合には、選挙のプロセスに瑕疵があったために、当選が無効になるという考え方をとっています。従って、連座禁止の例外ではありません。政治資金については、法律違反があったとしても当選とはおおよそ直接関係するとは言えないので、公職選挙法の考え方も直接は援用できまぜん。従って、連座制は法律論として導入できないということになります。
この点、容易に連座という言葉を伝える当初のマスコミの報道ぶりは、野党が使い始めたものだとしても、極めて奇異に感じましたし、あまりにも法律論に無頓着であったと指摘せざるを得ません。私には「〇〇党、市中引回し及び打ち首獄門の刑検討へ」みたいな江戸時代的なイメージに聞こえてしまいます。「いわゆる」連座と我々が言い始めたのは、本来であれば法律上の連座制では当然ないものの、既に連座制を導入しなければ無責任だとばかりに宣伝されてしまっていたため、本来は恥ずかしいことではありますが、分かりやすさを優先したものです。
このあたり、例えば実務WGの鈴木けいすけ座長が、「厳密な連座ではないが、いわゆる連座を導入する」と法律論としては極めて正しく記者会見で表明したら、某メディアは、「自民、連座制断念へ」というようなタイトルの報道でした。叩こうとするのは分からなくもないですが、「自民、打ち首獄門の刑断念へ」と同じですから、恥ずかしさ倍増です。
では具体的な監督責任強化はどのようにしたかと言いますと、会計責任者には代表者である政治家への報告義務を課し、それに対して政治家には会計責任者への確認書の提出義務を課しました。これによって、会計責任者と政治家の間に、必ずやり取りが生じることになり、知らなかった、秘書に任せていた、などは完全になくなります。
ただ、これに対して、確認書を提出するという形式的な行為だけでは、言い逃れは無くならないとの指摘が為されました。残念ながら、著名大学の著名な政治学者までもが、刑法の専門家ではないと留保しつつも、堂々と曖昧だと指摘するに至っており、少し考えれば分かるのにと思うと残念でした。まずそもそも形式的行為には刑罰はかけられません。従って、確認書というのは、実質的な確認行為を伴う義務が課せられます。一定のというのがミソで、立証責任は捜査機関ですが結構厳しい内容になっています。
現行法では、政治家の責任は、実質的に会計責任者との共犯のみに発生していたものを、監督責任そのものを刑事責任の対象にしたもので、捜査機関の対象になったということを政治家側が理解しなければなりません。この点、ザル法だと宣伝されたため、政治家が軽く考えはしまいかと懸念しております。繰り返しますが、今まで捜査機関の対象となっていなかった監督責任が捜査対象になり、疑惑が生じたらゴリゴリ絞られるということです。
一方で、秘書の嘘の説明を見破れなかった、などと言った言い逃れができるとの指摘もありました。誤解を恐れずに言えば、言い逃れが絶対できない刑罰条文はこの世に存在しません。義務が規定され、処罰が規定されると、あとは捜査機関の出番となります。例えが適切か分かりませんが、刑法には窃盗をした者は処罰すると書いてありますが、盗んでない借りたんだ、と言い逃れできる条文だからザル法だとはなりません。捜査機関の対象になっているところがミソなのです。
■改正の全体構造は「再発防止」と「透明性向上」
今回の改正は、事件を受けた再発防止の部分と、それとは直接関係ないものの透明性向上を目指した部分の2つによって成り立っています。前者の再発防止は、既に触れたように、現金管理原則禁止、監査対象拡大による監査強化、代表者(政治家)監督責任強化、パーティー事業における現金授受原則禁止、オンライン提出等義務化などであって、後者の透明性向上が、話題となったパーティー公開基準引き下げや政策活動費などになります。
再発防止については、自らの組織内で発生したことですので、責任をもって起案しましたが、透明性向上については、野党の皆様との協議によって決めることとなりました。この部分が、様々な議論を呼んでしまったように思います。
■政治資金パーティー公開基準引き下げ
まずこの公開基準について、民間では1円から領収書だ、という指摘がありましたが、そもそもこれは領収書の話ではなく、1つ1つの取引内容を全世界に公開する基準のことです。さすがに民間でも一つ一つの取引を全世界に公開することはないはずです。その上で、現行法では20万円とされている公開基準を、今回は他党の指摘があり5万円に引き下げることとなりました。実は実務者としては10万円を堅持していましたが、最終段になって総理の英断があったものです。
公明党を含めた他党が5万円を主張するなかで、なぜ我々実務者が10万円を主張していたのかについてふれますと、国会での公式答弁では、政治参加を委縮させる、寄附基準5万円は上回るはず、などの理由を提示しましたが、実体的には、参加者は公開を忌避するため、参加者も減りますが、裏を返せば政治団体としての収益は確実に落ちます。
私は、そもそも金のかからない政治を志向するのは当然と思っていますし、これだけの問題を起こしているのであるから、直接事件とは関係ない公開基準であっても、引き下げるべきは当然との思いはありましたが、個々の議員が政治資金を自己努力で集めにくくなれば、構造問題が生じるとも考えていました。
すなわち、第一には当然ですが活動が縮小する方向になること。政治活動が縮小すると一般的には国民から離れた政治になりますから中長期政策を志向する議員が増えるはずです。逆の場合は生活密着型の政策志向になるはずです。私は両者のバランスが大切だと思います。
第二に、必要経費を自らの努力で獲得できなくなる議員は、所属政党を頼るようになります。党への依存が高まるということは、党の方針に忠実な議員が増える傾向になると同時に、党役員への権力集中を生み出します。ただでさえ派閥が解消されたなかで、党役員に権力が集中しているのに、それ以上、構造的に権限を役員に集中させることが、健全な政党、健全な民主主義に繋がるのか、という問題意識です。
自民党は国民政党です。何よりも有権者の言うことを聞くという立場です。立憲や国民も見るところ恐らく同じような傾向にあります。その他は見るところ上意下達の傾向が強いように思います。従って、現時点でボトムアップ型の政党ばかりではないのも事実ですが、だからと言ってトップダウン型の政党ばかりにしてよいということにはならないはずです。
議論を拝聴するに、他党でこうした民主主義上の作用を熟慮した形跡は見当たりませんでした。政局として、政治的に自らに有利な環境を言葉で作っていくことが政治なのであれば、否定されるべきものではありませんが、政治的に他国よりも有利で健全な民主主義を言葉で作っていくことこそ、私は重要だと思います。
■第三者機関は重要だ
透明性向上については、批判が最も高かった政策活動費も含めて、第三者機関で担保するというのは非常に有効な方法であろうと思います。この第三者機関については、党内実務者間でも多少は議論されておりましたが、条文化は与野党協議を通じて、検討項目として附則に入れることになりました。
問題は、第三者機関に何を期待するのか、であって、その機能や権限については様々な方向があるはずです。そしてどのような機能や権限を付与すべきかは、まさにどのような民主主義を日本が作りたいのかに左右される問題です。
すなわち政党というものが存在悪で、厳しく規制したいのであれば、調査・通知・勧告は当然として、捜査機関への通報や公表も場合によっては考えなければなりません。加えて、情報保全の仕組みも整備すべきです。この場合、強力な権限が付与できる独立行政委員会の位置づけが望ましいわけですが、3権分立を考えた際に、政党が国家権力によって監視される国家というのは、民衆が国家権力によって縛られることに繋がりますので、どちらかというと権威主義国家型の味付けにならざるを得ません。
では、3権分立の中で同じ立法府である議会に、特別委員会を設置することも考えられます。ドイツは議長の下に監督機関を設置しているようで、常時監視というよりは状況に応じて調査する機能のようです。ただ、行政機関のような強力な権限を付与できるかは疑問です。また、特別の第三者監査機関を国家が指定するという方向もあります。即ち、国会議員関係政治団体に課された法定登録監査人制度の延長線上の話として、政党も監査を行うという方向です。
いずれにせよ、繰り返しになりますが、我々議会人が、一体どのような民主主義を作りたいかで大きく味付けが変わる制度になりますし、行政に置くとしたら相当な検討期間が必要になると想像できます。政局的な議論ではなく、静謐な環境で落ち着いた議論が醸成されることを切に願っています。