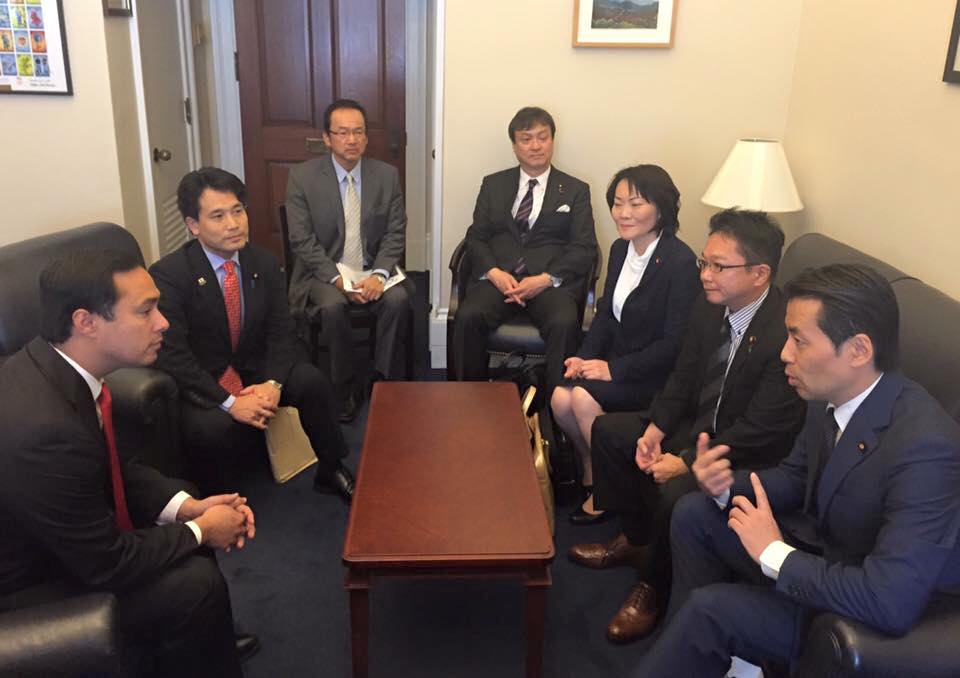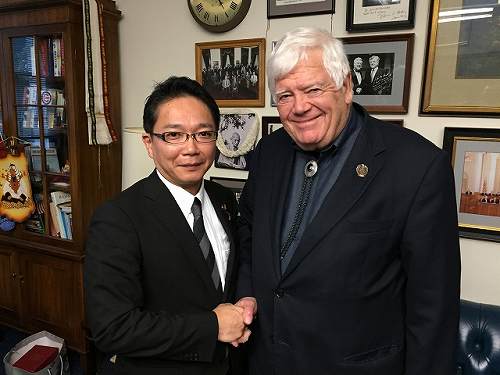保育に関する匿名のブログ書き込みが国会でも話題になっています。そこで改めて保育について考えてみたいと思います。
・待機児童問題。都内の切ない現状に接し
少し余談から入らせていただきますが、3年前、とある大使から意見交換したいとのことで大使館にお招きいただいたときのこと。夕方4時ころ、東京都内の初めて行くその住宅街にある大使館を探していたときのこと、「保育園建設反対」という一帯に掲げられている垂れ幕を見て、意味がよく呑み込めなかったことを今でも鮮明に覚えています。実に残念で切ない。
田舎育ちの私の感覚からすれば、子供たちの黄色い歓声が聞こえてきたら賑やかに活気づくのに、と。しかも子育て世代の親御さんも集まる。もう少し付け足しで言えば、まさに3世代交流というコミュニティにとってもっとも重要な循環ができるのに、と後で考えたものです。
一方で、都内に住むご年配世代にとってみれば、折角一生かけてローンを組んで静かな住宅街に庵を構えたのに、それが送迎の親御さんの車でごったがえしたり、子供たちの声を騒音と思ったりと、面倒だと思うこともわからなくもない。
仮にここで、ご年配世代には是非30年前とは全く異なる現在の子育て世代の苦しみを分かってほしい、なぜなら年金などの社会保障はこうした世代の負担の上に成り立っているのだから、と訴えたところで、そうしたご年配層にとってみれば、いやいや自分で長年積み立てた年金じゃ、とか、若い世代は日中仕事に行ってて保育所が近所に建ったら面倒だとも思わないだろうけどわしらは常に接しないといけないんじゃ、と言った主張になり、感情論になってしまいます。実は縁のある地域でも同様の問題が起きています。個別問題を解決できない力の無さを感じもしています。
人口減少対策議員連盟でまさにそのことが話題に上がり、我が意を得たりと政府に対する提言を事務局長としてまとめて提出したりしました。その部分の文言をそのまま再掲すると「子供は宝物だという社会意識が低下しており、例えば保育園騒音による住民の反対運動等の悲しい事実が顕在化しており、間接的に出産意欲の低下につながっている」。そうしたことが起こらない社会環境を整備するということに尽きます。
兎にも角にも、東京という街は、若年層にとっても(保育施設)、ご年配層にとっても(介護施設)、誠に生活し辛い場所になりつつあるのは事実です。だからこそ、地方創生と東京一極集中解消によって、そうしたアセットの利用の最適化をしなければなりませんし、そもそも家族とコミュニティが子育てをするのだという原点に戻らないといけないと強く思います。
ただ、現実がこうした理想に近づくのは少し時間がかかる。こうした演繹的視点だけでは社会問題は解決しない。だとしたら、もっと帰納的視点で解決を試みなければならないのは事実です。
・保育士の待遇は絶対に改善すべきだ。しかし・・・
まずは予算を増やすことです。OECD諸国の殆どが、仮にご年配層に10予算をとっていたら、3は子育てに予算を確保する。日本は1強です(少しデータが古いかもしれません)。未来への投資をしていかなければならない。高齢化が高齢者向け社会保障予算を増やし、それで若年層予算を減らし、子供が減り、高齢化が進む、という悪循環を断ち切ることです。少なくとも待機児童が多い地域については保育士の待遇は絶対に改善すべきです。
しかし、アセット(箱もの)をばんばん増やすことが正しい方策かと言われれば絶対に違うということを明言しておきたいと思います。
例えば政府も、こども子育て新制度を制定し積極的に予算も拡充しており、アセットも増えましたが、結局待機児童は増えている。利用したいと思う人にとって見れば、一億層活躍とか女性活躍っていうから就職活動して保育に預けようと思っているのになんだよ、となる。つまり、予算増やしたら余計利用希望者が増え、さらに予算を増やしたら、更に増える、という発散システムです。予算が増えるということは消費税も増えるということですから、折角働き始めたのにその稼ぎは公的負担として消えていく。何の為に働きに出たかがわからなくなります。
しかも、繰り返しになりますが東京など特に待機児童が問題になっているところに集中的にアセットが増えていくことになりますが、確実に需要はピークを迎える。地方はアセットが余る時代が確実にやってきます。であればやはり適正配置を考えるべきだと思います。待遇についても政府による過重な規制が悪影響を与えていると長年議論されていますが未だに答えはでていません。
要するに時間軸と地理的水平軸で最適なアセットにしないと現役世代の負担になるばかりです。
・政策の方向を見つめなおすべき
ではどうするべきなのか。現状の保育制度の補完機能として、特に需要が多い都会では、小規模保育やベビーシッター活用やシェアリングなど新しい流れを検討すべき時期に差し掛かっているのだと思います。でないと日本はもたない。シェアリングとは何のことかと言えば、子供を預かってもいいですよ、と思う人と、預かってほしい、と思う個人を繋げるビジネス。昔で言えば、地域に家政婦紹介所というのがありましたが、地域の面倒見の良い人がやっていたことをITで繋ぐということです。もちろん、質の面、安全安心の面で、ちゃんとした制度を作るべきは論を俟ちません。保育の規制はこの安心安全を担保するためにある。保育の質を国家が確保するということは当然です。
先日、Asmamaという会社の経営者と話す機会を得ました。その経営者の理念は、ビジネスチャンスということでは全くなかった。むしろ、社会の課題を解決する手段を提供しているというスタンス。誠に安心しました。その経営者曰く、利用者に安心を提供するために、つまり見ず知らずの人に我が子を預けるのはちょっとねという意見に対して、足を使ってコミュニティ単位で交流会を地道に行っているという。ITを使っているというだけで、結局家政婦紹介所とシステムは同じです。
こうしたプラットフォームを築くことを限定的にでも検討すべきです。その際は、責任所在や個人認証も含め、安心安全をどのように担保するかが中心課題になると思います。