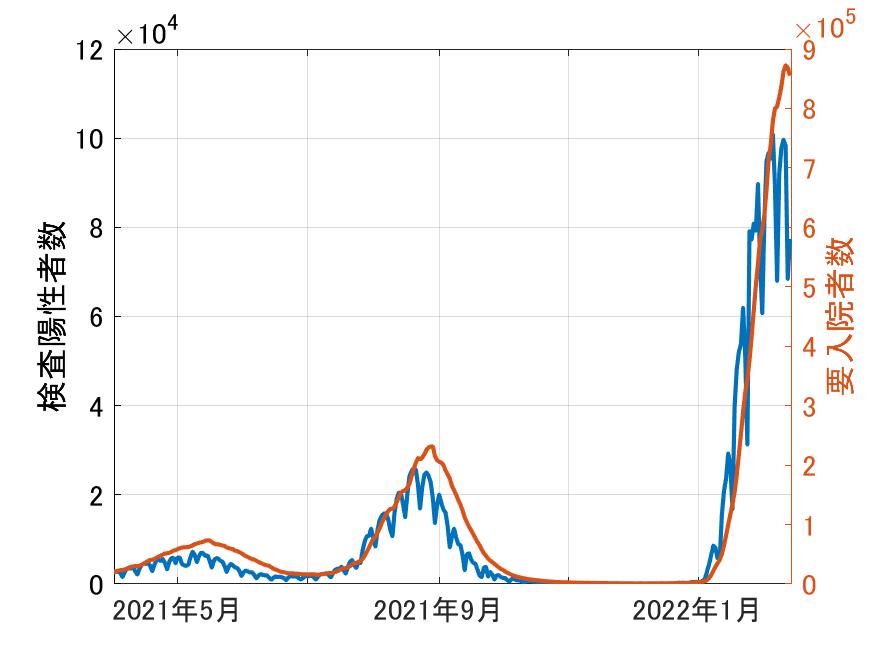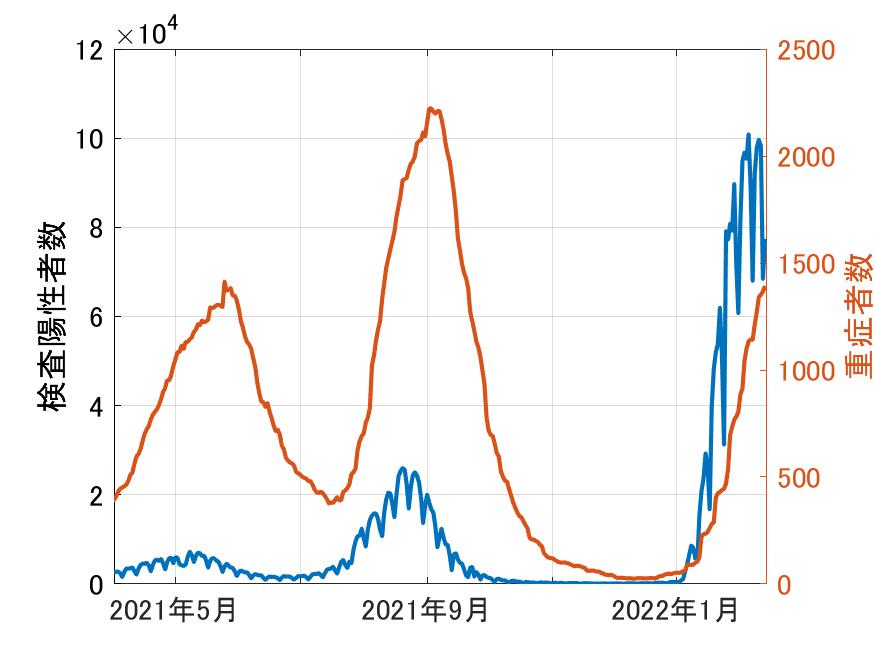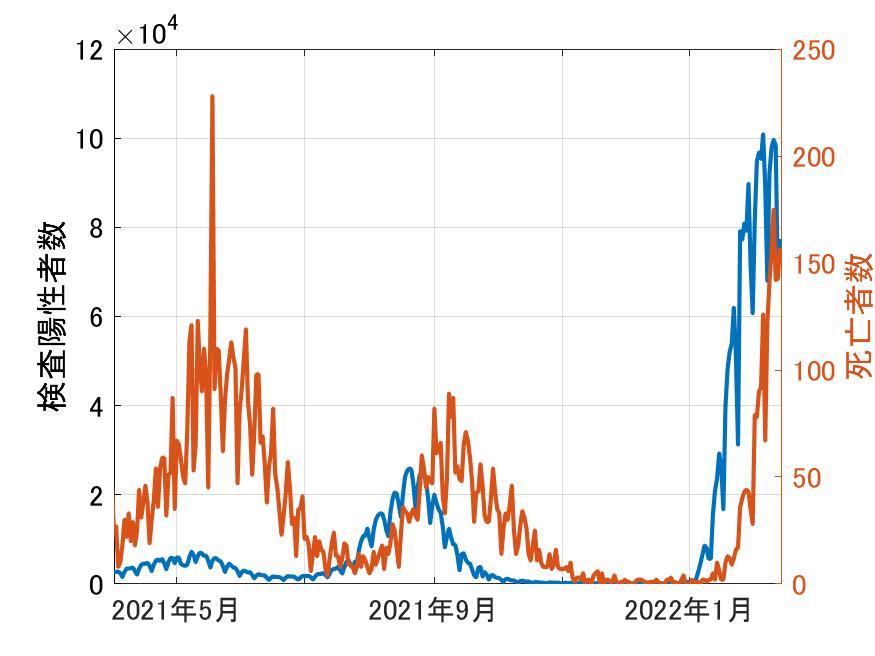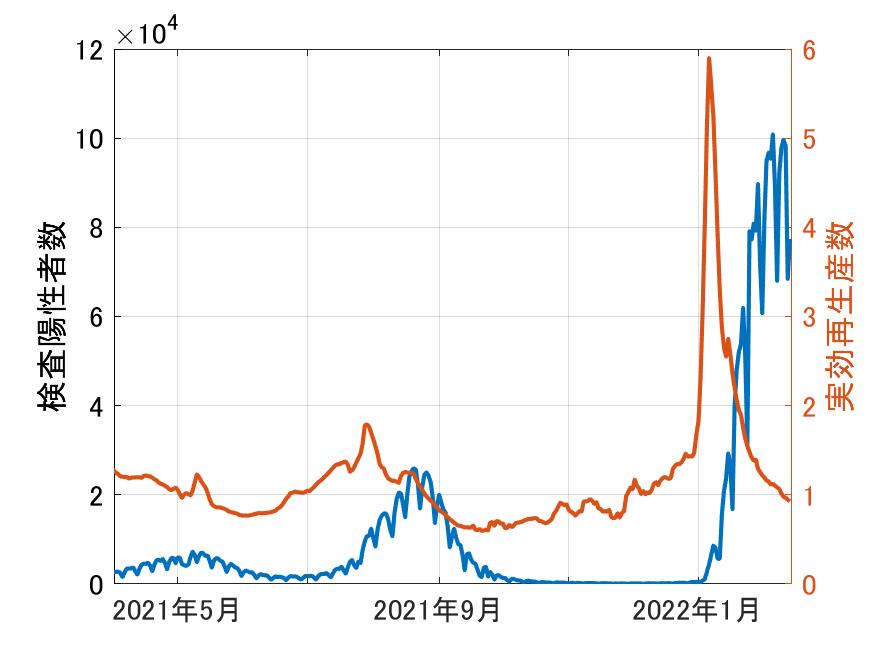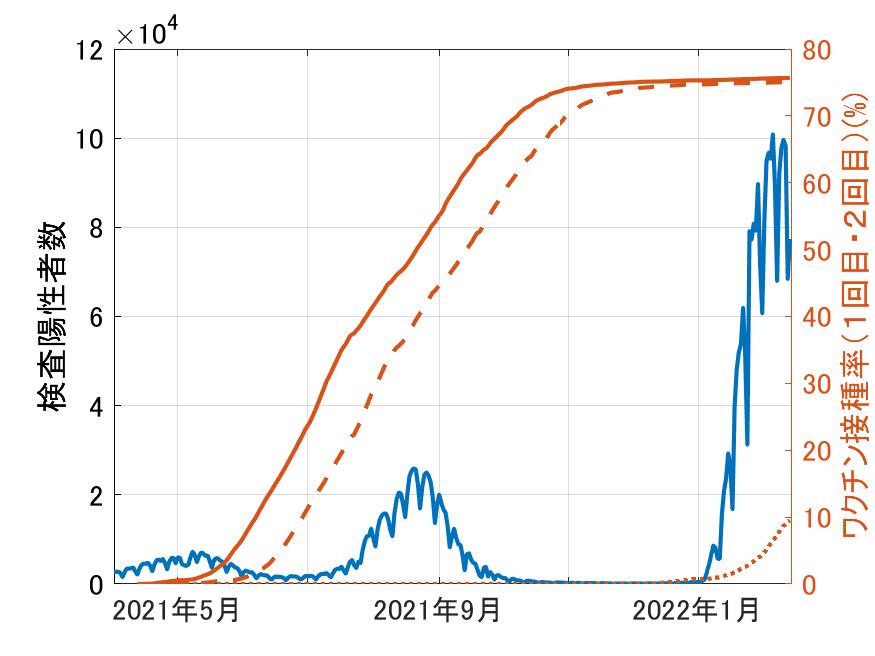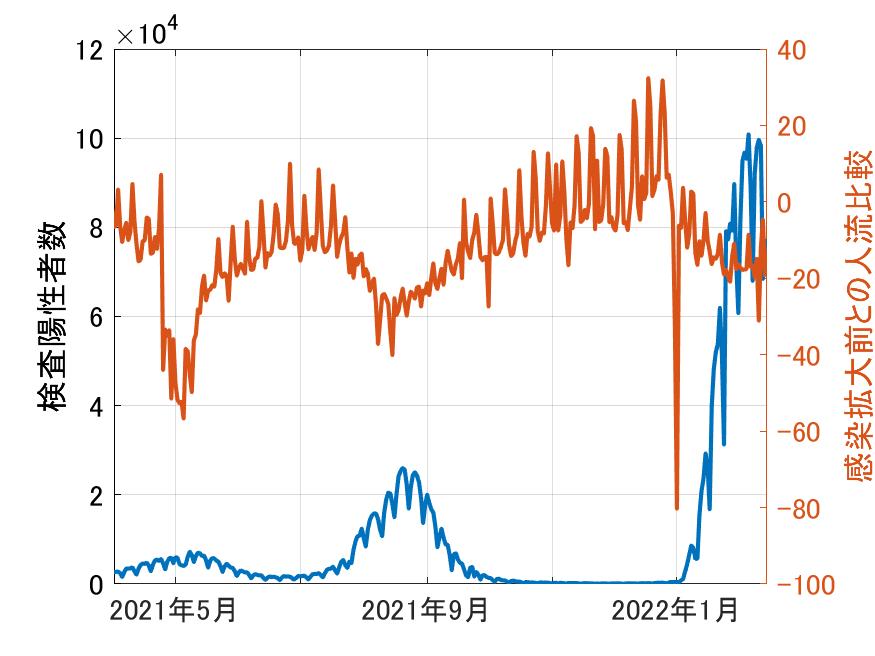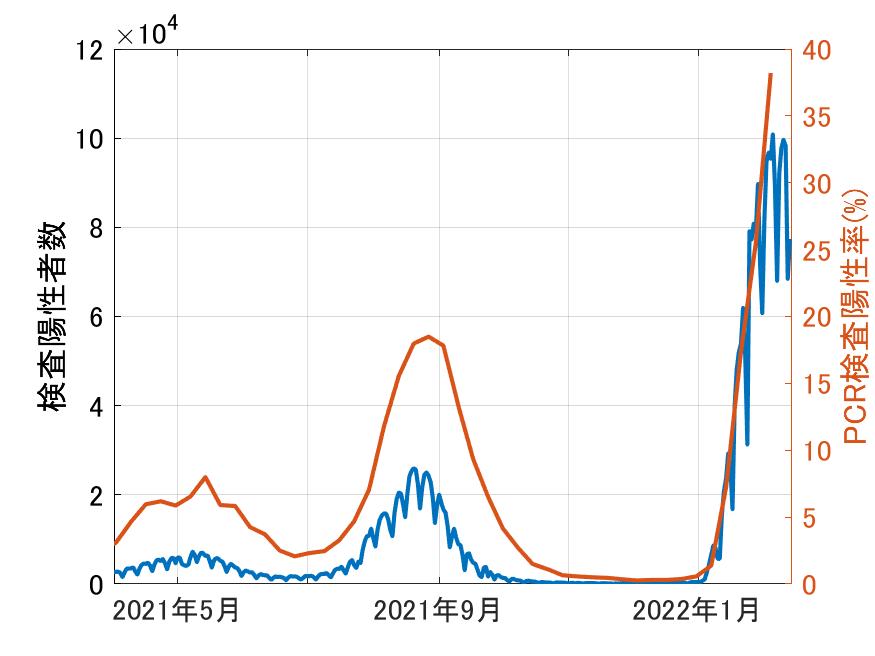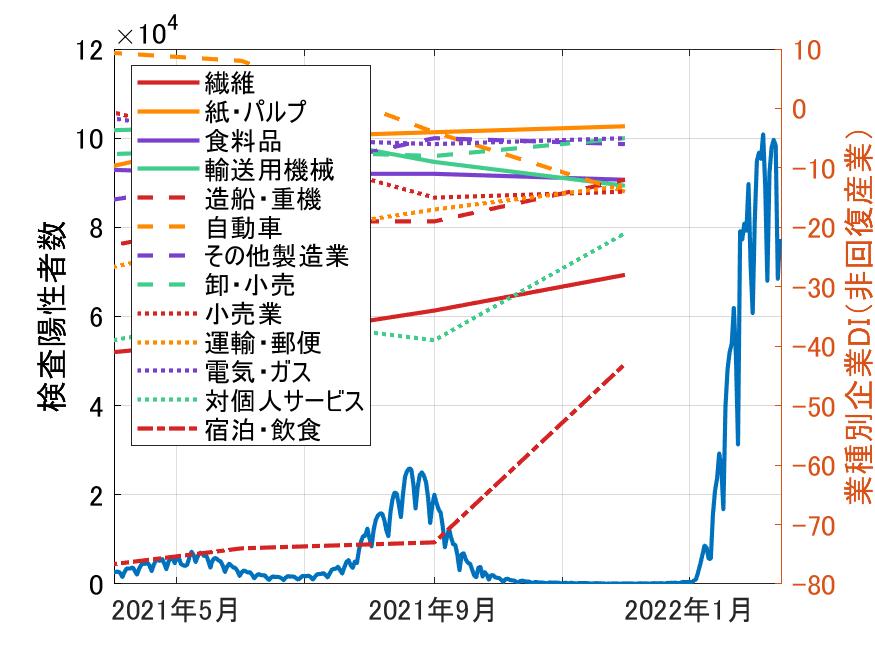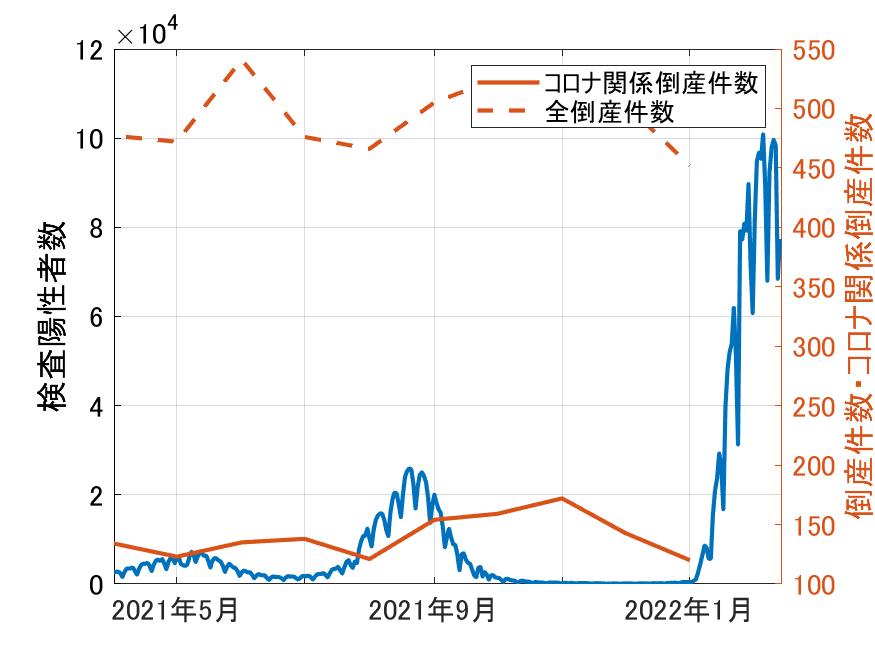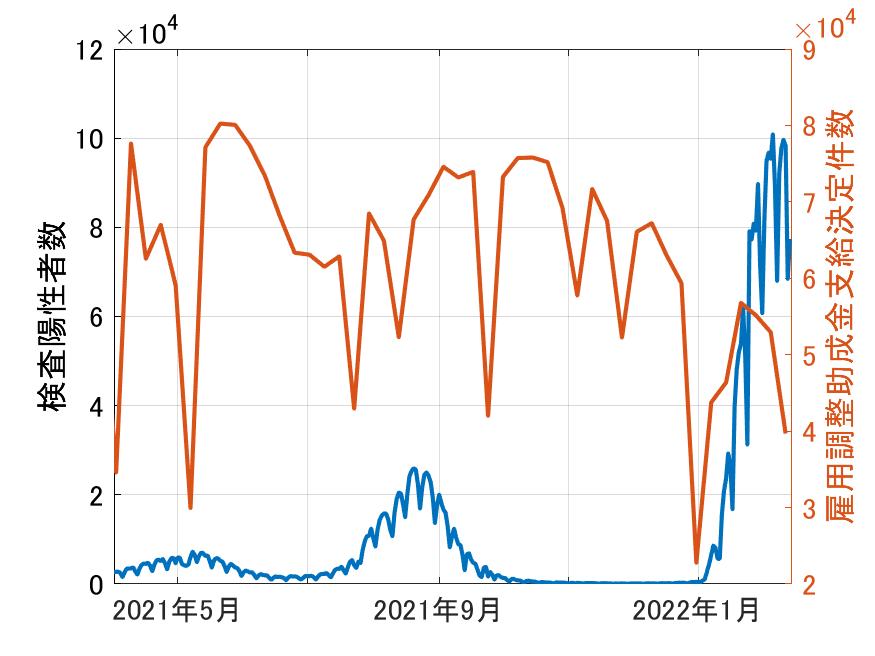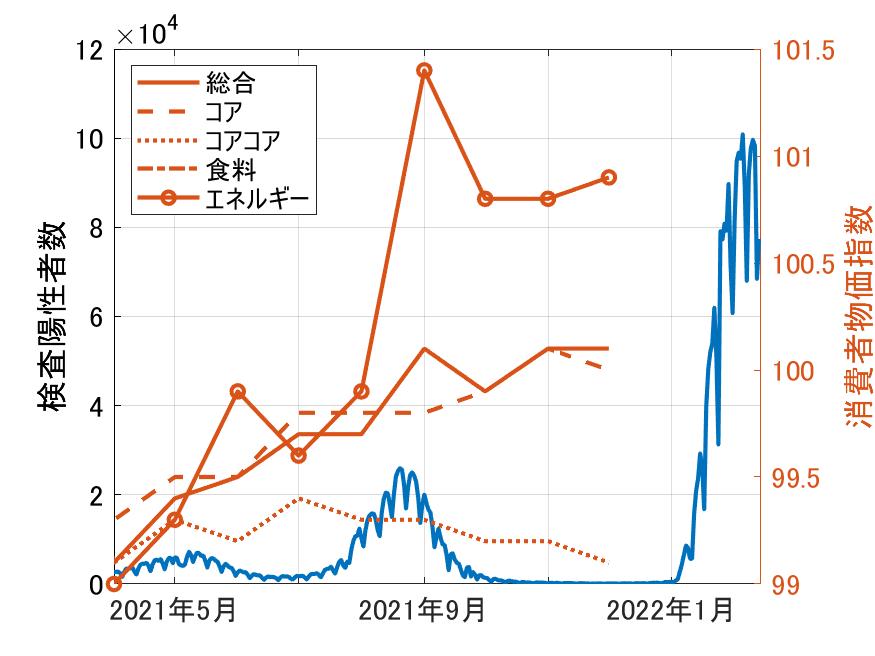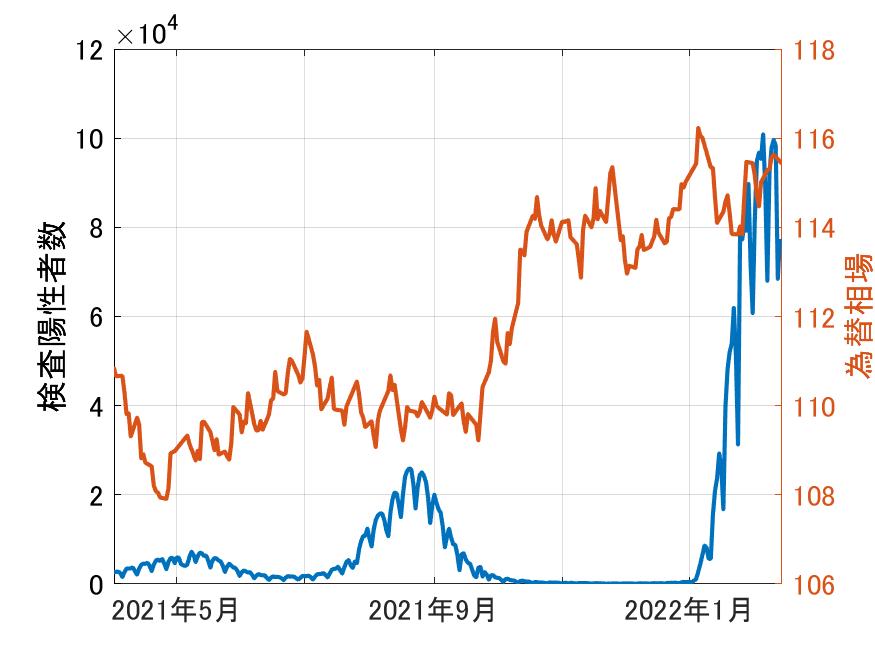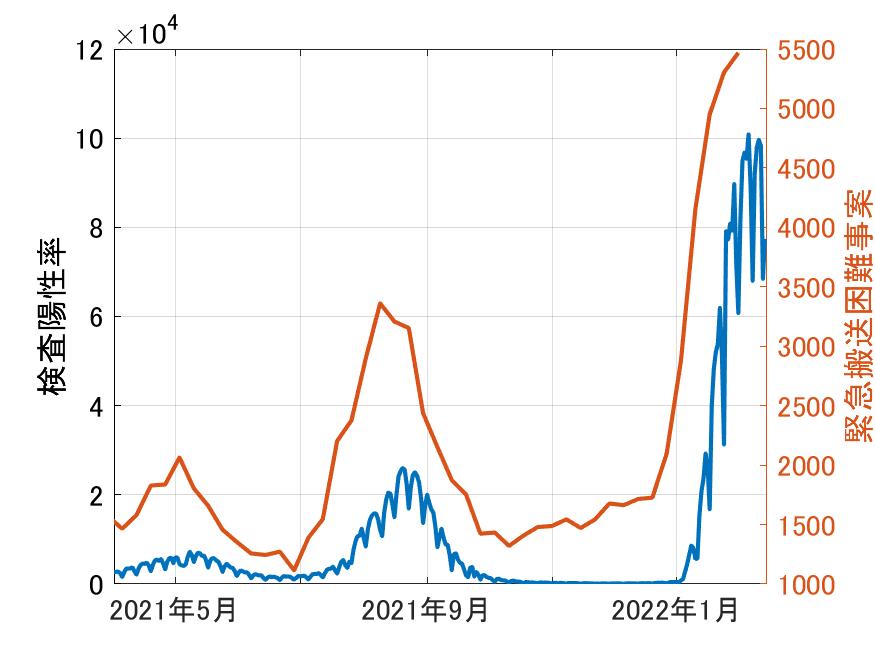■経済活動と安全保障のバランス
本法律は枠組みであって、具体的な規定はこれから集中的に議論し、定めていくことになります(政令や省令)。法律に具体的な事項を記載していないため、新聞紙面上ではあいまいだとの指摘をときどき受けますが、これは国際情勢や技術動向、民間事業の形態などに機動的柔軟に対応していくためであって、今後の具体化作業では可能な限り予見性を確保して参ります。一方で完全に透明にすれば、日本の脆弱性を世界にさらけ出すことになるため、慎重に判断せざるを得ません。
■経済活動の自由
経済活動への制約に対する不安視も一部見受けられますが、経済安全保障を目的化することは決してありません。すなわち、経済活動の制約を強め過ぎて衰退させれば守るべきものもなくなりますので本末転倒です。法律でも明記していますが、明記しなくても経済活動を最大化しつつ安全保障を確保する方針です。経済活動は基本的に自由が確保されるべきものという考え方が土台にあります。
■米中対立との関係
また、米中対立を背景とした、いわゆるグローバルサプライチェーンのデカップリングとの関係についてのご指摘を受けることもありますが、本法律は特定国を対象としたものでもなければ、デカップリングを前提としたものでもありません。あくまで我が国独自の経済安全保障の考え方に基づいてスクリーニングを行った結果として適用が決まるものです。
■自由貿易との関係
また全てのグローバルサプライチェーンを自国回帰誘導するものでもなければ、自国主義を採用するものでもありません。自由貿易推進の旗印は明確に振りつつ、それでも経済安全保障上、自由を限定的でこそあれ制限しなければ秩序確保が困難な領域を対象とするものです。この考え方については、本稿最後に更に深く掘り下げます。
■経済安全保障とは
経済安全保障とは、分かりやすく言えば国益を経済面から確保すること、と小林大臣は説明しています。では国益とは何かと言えば、現行の国家安全保障戦略に定義されている通り、国家の主権独立と国民の身体財産を守ること、経済的繁栄を実現すること、そして基本的価値やルールに基づく国際秩序を擁護し強化することです。
■経済面で国益をどのように確保するか
では国益を経済面から確保するとはどういうことを指すのかと言えば、一言で言えば、他国の動向に左右されることなく我が国が主体的に未来を決定できる環境を整える努力をすることです。例えば他国に過度に依存している重要物資があったとすれば、我が国が主体的に未来を選択できなくなります。すなわち、経済面から国益を守るためには、戦略的自律性の確保、戦略的不可欠性の確保、そしてそれらを通じた国際ルール形成、が中心的な考え方になります。戦略的自律性は字義通りですが、戦略的不可欠性とは、世界にとって日本がなくてはならない存在になる環境を整えることです。
■本法律は経済安全保障政策の一部をなす土台
本法律は、恐らく世界初の一括推進法で、担当大臣の設置も併せて世界から注目されていることを実感します。ただ、一括というのはこれら経済安全保障全体を網羅的にすべてという意味ではなく、あくまで、直ちに法的担保が必要な項目を束ねた、という意味です。従って、本法律は、我々の考える経済安全保障全てをカバーするものではなく、むしろ基礎の一部であって、今後も国民の皆様のご理解を得ながら必要な改正は行っていくこともあるはずですし、法律を必要としない様々な施策も必要となります。
■本法律が対象とするのは外部起因のもの
経済安全保障を要因別に二分すれば、外部起因(外国勢力によるもの)と内部起因(国内事情)に分けられます。本法律で担保したものは、前者の外部起因のものです。外国勢力による経済的手段によって国益が損なわれる恐れがある場合を基本的には対象としたものです。
■本法律が規定する具体的な項目
少し具体的な話に入りたいと思います。本法律では、法的担保が直ちに必要と考える項目、すなわち基幹インフラサービスの安定的提供の確保、重要物資のサプライチェーン強靭化、重要技術研究開発の官民協力、特許出願非公開、について規定しています。
なぜこの4つなのか。経済活動や国民の生活が脅かされる可能性があるとすれば、それは第一に、電気、水道、ガスをはじめとした、これまでも業法規制がかかっているような基幹インフラサービスです。第二には、業法規制はないものの安定供給が確保されなければ重大な影響がでる重要物資の安定供給確保。第三に、そもそも日本独自の戦略技術を保有することを考えなければならず、それが官民技術協力。そして第四に、そうした技術があったとしても技術流出防止を講じる必要があるという観点から、法改正が直ちに必要なものとして特許制度の抜け穴を塞ぐ、という考えです。念のため繰り返しになりますが、法律が必ずしも必要ない措置も、実施しているか実施予定ですし、今後も必要に応じて法律改正を行って参りたいと考えています。
■基幹インフラ
電気や水道などの基幹インフラ事業については、本法律では14業種を指定しています。これらは既に業法規制がかけられている業種ですが、既存の業法規制には他国からの妨害行為に対処すべき義務が課せられていないため、安全保障上の上乗せ規制をしたものです。近年、他国によるサイバー攻撃などで基幹インフラの安定供給リスクが高まっていますが、国民からすれば安定供給が強化されるということになります。
14業種に該当する全ての民間企業が対象になるわけではありません。しかし対象となる範囲を規模などで一律に線引きするのも困難です。それは、規模や地理的分散といった市場構造や、設備の利用形態、また経済活動や国民生活に与える影響程度が業種ごとに異なるからです。
今後、それぞれの業種ごとに、利用者数や取扱量やシェアなどの事業規模や代替可能性について、事業者とよく相談しながら基本指針で基準を定めていくことになります。対象事業者は、特定重要設備をこれから導入しようとする場合、もしくは維持管理を外部に委託する場合には届出が必要となります。
特定重要設備は、外部からの妨害行為の手段として利用され得る設備であってその機能が停止低下した場合にサービス提供に著しい影響を及ぼし得るものとして、具体的に技術内容も含めて業種を所管する省庁の省令で定められます。事業者の負担に十分配慮するとともに国際ルールとの整合性を確保しつつ、念のため事前相談制度も設けています。
■サプライチェーン強靭化
重要物資サプライチェーンについては、一番分かりやすい例が手術で使う医療用抗菌薬など、原材料を特定国に過度に依存していたケースがあり、その場合は首根っこを掴まれているのと同じ事ですから、こうした事態を回避するため、取り扱い事業者を支援するのが制度の趣旨です。すなわち放置すれば、そうした事業者が経済合理性の判断から、供給しないか他国依存から脱却できないなどの状態を改善するための措置です。
特定重要物資の指定の基本的考え方は、今後、基本指針で、また物資毎に支援方法などを取組方針などとして所管省庁の省令で定めることになります。その後、その特定重要物資を供給しようとする事業者が申請を国に提出、国が認定すれば、その事業者には定められた一定の支援が提供されることになります。該当事業者が不在の場合には、特別の場合として国が直接、物資の安定供給に乗り出す仕組みです。
物資指定に当たっては、当然ですがサプライチェーン調査が大前提となります。その調査権限を法的に担保しています。その上で、物資指定の基本中の基本の考え方は、その物資の重要性、供給リスク、外部行為リスク、そして必要性と効果を見て判断する方向です。重要性というのは、国民の生存に不可欠であるとか広く国民生活や経済活動が依拠する物資、幅広く普及利用されている物資、が対象となります。供給リスクについては、特定少数国にサプライチェーンが過度に依存しているか依存するおそれがある物資、であって、その依存度や他国代替性、物資自体の代替性や国内調達の容易性、または影響度と影響範囲などで判断していくことになります。外部行為リスクについては、外部からの影響を総合的に判断していくことになります。そして最後の必要性と効果については、他に担保する制度がないなど、この法律で担保する必要性があることや、本法律で実体的な効果がある場合に絞っていくことになります。具体的な指定は、ざっくりと物資全体を指定することも考えられますが、性質に注目するとか、用途や性能、材料や装置に注目することも考えられます。
支援措置として具体的に何をするかと言えば、冒頭に示したように国内回帰だけを目指したものではなく、物資の特性に応じて、多様な措置を講じるものです。1つはサプライチェーン強靭化として、生産基盤整備、供給源多様化、備蓄、生産技術の導入や開発改良など、また指定物資の依存度低下を図るために、使用合理化や代替物資開発などに対する支援も可能にするものです。具体的には、別途申請に応じて指定する安定供給確保支援法人を介した助成や利子補給、SBICを介した中小企業対象の株式買い取り支援、日本政策金融公庫と民間金融機関を介したツーステップローンのほか、公正取引委員会との関係整理、関税定率法との関係整理などです。支援法人には基金を積むことも可能としています。
■官民技術協力
重要技術の研究開発を推進するための官民協力の枠組みを法的に担保するための規定です。例えば、AIや量子、バイオなどです。バイオは今後幅広い領域で社会に重大なインパクトを与える技術とされていますが、例えばコロナワクチンでは、我が国は他国に完全に依存する状態を2年以上に亘って続けています。逆に日本だけがワクチンを作れたならば、戦略的不可欠性を確保することになります(必ずしもワクチンを指定するということではありません。ワクチンは既に別のプログラムで推進しています)。こうした日本の強みを伸ばし、ひいては日本が世界の中で必要不可欠な存在とされるような技術を戦略的に強化していくことを狙ったものです。
今までに決定的に欠如していた仕組みが研究開発サークルの情報保全の制度化です。民間企業や研究者と政府が、それぞれ会社の営業秘密や公開したくない独自の研究手法や機微情報などを、相互に安心して円滑に交換する枠組みを創設し、研究開発、成果創出、社会実装の加速を狙ったものです。情報保全については当然ですが、官民の関係者が協議会を構成したのちに、協議会が必要と判断した場合にだけ保全義務がかかりますので、突然政府が民間研究者に保全義務をかけるわけではありません。対象は、先端的な技術であって、使用技術情報が外国に悪用されれば安全が損なわれるような技術です。基礎研究というよりは、技術成熟度が一定程度あるけれども社会実装までには至らないレベルを想定しています。
また国際的な研究動向や国際情勢を内外調査機関と連携しながら分析し、必要な政策提言を行うシンクタンクを創設することとしています。所望の機能を発揮するには時間がかかりますが、何よりも人材育成が必要であり、そのためには相応の権限を付与することも考えられます。
■特許出願非公開制度(技術漏洩防止措置の一環として)
日本の特許制度には欠陥がありました。特許は当然、公開が原則です。特許制度の本質は、発明を公開することで知恵を共有し社会発展を促す代わりに、その代償として発明者には期間限定の独占的な権利を付与するものです。だから公開は大前提になります。一方で、悪用され得る技術も世の中多くあります。従って、多くの国では、例外として出願を制限していますが、日本にはその制度がありませんでした。
制限と言っても、出願公開の手続きを留保し情報保全する措置なので、期間が過ぎれば出願手続きが再開され、通常プロセスに乗りますので、決して突然政府から秘密指定されて蔑ろにされ闇に葬られるような制度ではなく、主要先進国と同等の制度になるだけです。
具体的には、今後、まずは対象となり得る技術分野を指定します。基本的には国家国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明ということにしておりますが、それでは広く網がかかり過ぎてしまい産業の発達に及ぼす影響が大きくなりすぎる場合があるので、軍事技術に限定するなど付加要件を付すことにしています。対象分野については外国出願制限がかかることになります。
特許庁は、受理した出願をその特許分類を用いて機械的にスクリーニングし、対象となり得る出願であれば、本人に通知するとともに内閣府に出願を回送、出願人に出願を維持するかどうかを確認した上で、本人了解のもと守秘義務をかけたのちに保全審査のプロセスに入ります。保全審査では産業に及ぼす影響と安全保障上の影響を判断した上で、保全指定をします。期間は原則1年で更新可能としています。保全指定までの審査期間は本則特許制度との関係で10カ月以内としています。
もちろん出願手続きの制限をかけるわけですから、因果の範囲内でそれなりの損失補償を想定しています。また、たまたま同一の出願を先願者の存在をしらずに行った時の権利関係についても念のため規定しています。この辺りはマニアックな話となりますので割愛します。
いずれにせよ、この措置にて特許制度を通じた技術漏洩に蓋が閉められることになりますが、これで完全に漏洩が防げるものではありません。あくまで、特許制度という国の制度を介して公然と技術流出が行われる理不尽さに対処するための法整備です。
■(余談)自由と管理・社会とコスト
経済活動と国際秩序が密接な関係にあることは歴史が証明しています。自由貿易による国家同士の相互依存が国際秩序の安定化に資することは近年までの常識でした。過去に人類は、経済活動の制限が、国際秩序の不安定化に繋がり、大戦に至った経験をしました。しかし最近では、新自由主義と過度なグローバル化が各国国内の賃金格差を生み、国内政治の先鋭化とともに自国主義への傾倒とブロック経済化を通じた国際秩序の不安定化も経験しています。従って管理された自由とバランスが必要なはずです。WTO改革しかりDFFTしかりです。例えば自由貿易と一言で言っても、自由貿易にもルールがあり、ルールが国際秩序形成にマッチしていないのであればルールを改革するとも言えます。問題は同じルールに乗らない勢力が複数存在することです。
先端技術に多額の投資を行い富を享受している国があったとして、それが外部から搾取され富が遺漏しているのだとすれば対価を要求するのも当然と言えます。経済的外交圧力によって影響力行使を試みる勢力があったとするならば、それに備える努力をするのも当然です。違法に行われているのだとすれば管理するのは当然です。国際社会としての問題は、その行き着く先がどこにあるのか、最終的に社会にとってプラスになるのかマイナスになるのか、管理すべきだとしたらその対象はどこで、どのようにバランスをとるのか、であって、それらを慎重に分析すべきです。そしてより本質的には、どのような社会を目指しているのか、本法律案の施行を通じて、どのような国際ルールを形成するのか、社会にどのようなインパクトを生じさせるのか、社会の思考パターンがどのようになるのか、を注意深く考えていかなければならないのだと思います。
一方で、経済安全保障政策の一部は、カーボンニュートラルや防災BCPとならんで、単純に考えれば民間企業にとってはコストと映る課題です。これを時間軸のROE積分値の最大化と考える社会にしていかねばなりません。経済学的には外部不経済の内部化であって、新しい資本主義にも通ずる考え方であり、国際社会の潮流であるとも思います。